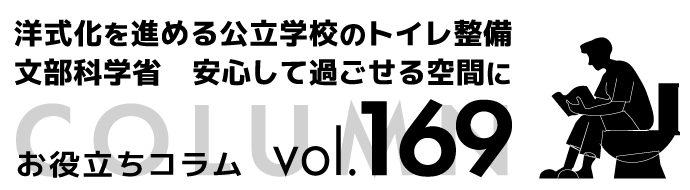
「和式トイレ」に慣れましょう
耽美派の文豪・谷崎潤一郎はその著「陰影礼賛」の中で、自身が思う「良いトイレ」のあり方を、次のように書いています。
「ああいう場所は、もやもやとした薄暗がりの光線で包んで、何処(どこ)から清浄になり、何処から不浄になるとも、けじめを朦朧(もうろう)とぼかしておいた方がよい。まあ、そんな訳で、私も自分の家を建てる時、浄化装置にはしたものの、タイルだけは一切使わぬようにして、床には楠の板を張り詰め、日本風の感じを出すようにしてみたが、さて困ったのは便器であった。と言うのは、ご承知の如く、水洗式のものは皆真っ白な陶器で出来ていて、ピカピカ光る金属製の把手などが付いている(中略)照明にしろ、煖房にしろ、便器にしろ、文明の利器を取り入れるのに勿論(もちろん)異議はないけれども、それならそれで、なぜもう少しわれわれの習慣や趣味生活を重んじ、それに順応するように改良を加えないのであろうか」。
この時代の便器ですから、いわゆる陶器製の「和式」と見るのが普通でしょう。
ところで文部科学省では、公立小中学校施設のトイレ整備の一環として「洋式化」を進めています。2023年9月1日現在の調査では、男子の小便器は別として、全体の約7割が洋式化されていることが分かりました。逆に言えば、まだ3割は「和式」ということになります。
単なる「和式」と「洋式」の違いだけだろうということも言えますが、実は今の子どもたちにとっては深刻な問題になっています。「和式」で用を足したことがないため、トイレに行くのをがまんして体調をくずすといったことが起きているらしいのです。そのため就学前の子どもに、和式トイレに慣れ、用を足すことを覚えてもらうという必要が出てきたというのです。このことで、今の子どもたちのトイレの習慣は洋式であることを、改めて確認することとなりました。
トイレ実態調査
前項で「3割が和式」と書きましたが、それをもう少し詳細に見てみます。
文部科学省によれば、公立小中学校のトイレの全便器数は約133万基で、うち洋便器数は約91万基、68・3%を占めました。逆に言えば和便器数は約42万基、31・7%となります。3年前の調査に比べ洋便器の占有率は11・0ポイントアップしました。
これを学校別に見ると、小中学校は総設置数が132万6336基、うち洋式は90万5447基で、その割合は68・3%となり、前回調査からの上昇率は11・3ポイント、同様に幼稚園は3万0871基のうち洋便器は3万7637基で81・0%、上昇率は6・2ポイント、特別支援学校は4万3990基のうち洋便器は4万9740基で88・4%、上昇率は9・0ポイントとなっています。この結果では、小中学校の割合の低さが分かります。それでも2016年度の洋便器率は43・3%と半分に満たなかったわけですから、洋式化は着実に進んでいるとは言えるでしょうが、文科省はそれをさらに加速し、「トイレの整備について、各地方公共団体の整備方針に応じ、児童生徒等が安心して過ごせるよう、財政面も含め、引き続き支援する」こととしています。
そのため大規模改造(トイレ改修)に対し、トイレ環境改善のための、全体的な改修をする場合には国庫補助(学校施設環境改善交付金)することにしています。その工事内容は①和式から洋式便器等へ交換する工事②便器等の設備、給排水設備、電気等の付帯設備の改修工事③床・壁・天井・建具等の内装の改修工事④間取りを変更する工事⑤その他トイレ改修に関連する工事――の5点としています。
バリアフリー化の現状
トイレの改修はバリアフリー化にもつながります。実際、文科省は2025年度末までに、避難所に指定されている全ての学校のトイレをバリアフリー化するという整備目標を掲げています。
2024年9月1日時点での達成率をみてみると、校舎は2万7342棟のうち2万0325棟で74・3%、屋内運動場は2万7137棟のうち1万3010棟で47・9%となっており、屋内運動場の達成率が低いことが分かりました。
ちなみにバリアフリー化する施設としては、全ての学校に整備する、スロープによる段差解消(「門から建物の前まで」と「昇降口・玄関等から教室等まで」)、要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校に整備するエレベーターがあり、学校施設のバリアフリー化に関する実態調査を通して整備状況が明らかになっています。
例えば、校舎の場合、スロープは「門から建物前」が84・7%、昇降口・玄関から教室までが65・2%、エレベーターは31・2%、屋内運動場ではそれぞれ80・7%、65・5%、72・1%となっています。
2025年度末までのバリアフリー化予定を見ると、校舎ではトイレが2・8ポイント増の77・1%、スロープ(門から)が0・9ポイント増の85・6%、同(昇降口から)が2・2ポイント増の67・4%、エレベーターが1・7ポイント増の32・9%となる見込みです。同様に屋内運動場ではトイレが3・4ポイント増の51・3%、スロープ(門から)が0・9ポイント増の81・6%、同(昇降口から)が1・9ポイント増の67・4%、エレベーターが0・3ポイント増の72・4%を見込んでいます。同省が掲げた目標は全項目で100%ですから、この数字は「バリアフリー化が進んでいない」と判断され、今夏をめどに次期整備計画が策定されることになりました。
終わりに
「御不浄(ごふじょう)」と呼ばれたり、「神様」や「花子さん」がいると言われたりしているトイレですが、今後の整備方針はどうなっているのでしょうか。実態調査では、この点についても触れています。
結果では、小中学校では「洋式化率90%以上」と「同80%以上」「60%以上」の合計は全体の92・0%、幼稚園は94・3%、特別支援学校は95・5%という高い数値になりました。とはいえ、まだ少しは「和式」が残るようです。そこには「知らない人が座った便座にお尻が触れるのが嫌だ」といった理由があるのかもしれません。
いずれにせよ、バリアフリー化も含めて、公立学校のトイレ改修は進められていくのは確実です。どういうトイレなら安心して過ごせ、用が足せるのか。大人が一律で決めるのではなく、それぞれの年代の意見を聞くことが大切です。少なくとも子どもたちにがまんを強いるトイレは言語道断でしょう。「トイレとはこういうもの」という画一的な発想は、やめた方がいいのかもしれません。
 執筆者
執筆者
顧問
服部 清二 氏
中央大学文学部卒業。設備産業新聞社を経て建設通信新聞社へ。
国土庁(現国土交通省)、通産省(現経済産業省)、ゼネコン、建築設備業、設備機器メーカー、鉄鋼メーカー、建設機械メーカーなどの取材を担当。特に建築設備業界の取材歴は20年以上にわたる。
その後、中部支社長、編集局長、企画営業総局長、電子メディア局長兼業務総局長を歴任、2019年6月電子メディア局の名称変更に伴い、コミュニケーション・デザイン局長に就任。建設通信新聞「電子版」、「月刊工事の動き」デジタル、講演集や各種パンフレットの作成、協会機関誌の制作、DVD撮影などを行う部署を管轄した。2021年7月から現職。










