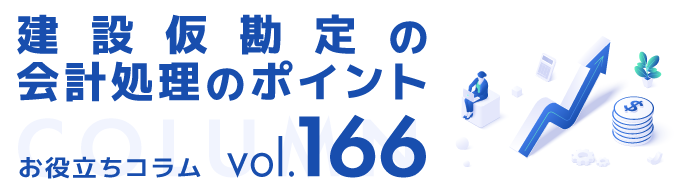
1.はじめに
建設仮勘定は製作中の有形固定資産にかかる勘定科目であるため、建設業側の経理担当者にとってはあまり馴染みがないと感じる方も多いかもしれません。一方、建設業の顧客側ではこの勘定科目が発生することが多く、固定資産の中では特に誤りが生じやすい項目の一つです。
そこで今回は建設業に深くかかわりのある建設仮勘定について、会計および税務の観点から解説したいと思います。
2.建設仮勘定の定義と分類
建設仮勘定とは、建設中の建物や構築物、製造中の機械装置など、未完成の有形固定資産に関する支出を一時的に記録するための勘定科目です。たとえば建物等は完成前に多額の支出が発生し、完成までに時間もかかります。そのため、部分的に支払った金額を前払金といった科目に計上してしまうと、会社の貴重な資金が何に投資されたのかステークホルダーには分かりにくくなってしまいます。しかし建設仮勘定に計上することで、その支出が有形固定資産に投資されたということを示すことができます。つまり会計上の観点からいえば、財務諸表利用者に対して、支出した金銭が何に投資されているのかを適時適切に表示することが可能になります。
建設仮勘定が使用される主なタイミングは以下の2つです。
①固定資産の完成前に支払を行ったとき
(借方)建設仮勘定 ×××/(貸方)現金預金 ×××
②固定資産が完成したとき
(借方)固定資産(建物など) ×××/(貸方)建設仮勘定 ×××
完成前の固定資産であるため、建設仮勘定の対象は建物とその付属設備、構築物、機械及び装置とその付属設備、船舶及び水上運搬具、車両などの陸上運搬具、工具、器具及び備品、土地といった有形固定資産に関連するものになります。したがって、販売目的の資産は対象外となり、顧客から受注を受けて完成後に引き渡す建物等に支払を受けた場合は棚卸資産(未成工事支出金)に計上されることになります。また、建設仮勘定は有形固定資産に関する勘定科目であるため、自社利用のソフトウェアに関する支出は、ソフトウェア仮勘定に計上されます。
上記の仕訳の通り、これらはあくまで仮勘定であるため、該当する固定資産が完成した時点で本勘定に振り替える必要があります。
3.建設仮勘定の会計処理におけるポイント
建設仮勘定を会計処理するうえで注意すべき主なポイントは、以下の通りです。
A.減価償却は行わない
固定資産は事業の用に供された日から減価償却費を計上しますので、建設仮勘定に計上されている限り減価償却は行われず、損益計算書に影響を与えることはありません。
B.減損損失の対象となる
該当資産の完成前であっても、収益性の低下により投下資本の回収が見込めなくなる場合があります。そういったケースでは建設仮勘定であっても減損損失の対象となり、通常の固定資産と同様に減損判定を行い、回収可能額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を計上しなければなりません。
C.資産除去債務の対象となる
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発、または通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令または契約により要求される法律上の義務、もしくはそれに準ずるものです。たとえ完成前の建設仮勘定であっても資産除去債務の対象となりますので、将来の除去費用を合理的に見積もり、割引現在価値で評価したうえで資産除去債務を計上します。
D.固定資産税の申告
1月1日時点で完成前の固定資産には固定資産税は課税されません。ただし、完成しているにもかかわらず振替処理を失念して建設仮勘定に計上されたままになっている場合は課税される可能性があるので注意が必要です。
E. 消費税仕入税額控除のタイミング
建設仮勘定に計上されているものについても他の課税仕入れと同様、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることができます。ただし、「建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供または一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとしないで、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の属する課税期間における課税仕入れとして処理する方法」も認められています。いずれの方法を選択しても問題ありませんので、実務上煩雑にならない方を会社の方針として採用することをおすすめします。
4.おわりに
建設仮勘定は支出を伴うにもかかわらず費用化されないため、不正に利用されやすい勘定科目といえます。そのため、費用処理されるべきものが建設仮勘定に混入していないか、逆に建設仮勘定として資産計上すべきものが費用処理されていないか、固定資産への振替が漏れていないか、といったことを決算時などに定期的にチェックすることをおすすめします。特に長期にわたって建設仮勘定に残っている項目などは重点的に内容を確認しましょう。そのためにはプロジェクト毎に管理可能な台帳を作成するなど、管理体制を整えることが重要です。

北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。

PickUp!
建設業会計とは?
~基礎知識からおすすめ会計ソフトまで~











