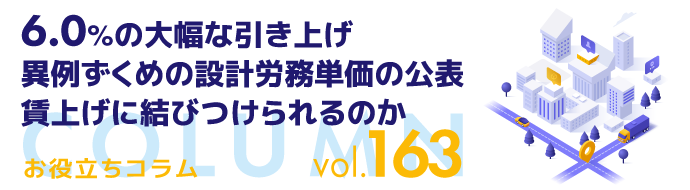
国土交通省は2025年2月14日、2025年3月から公共工事の積算に適用する設計労務単価と設計業務委託等技術者単価を公表した。設計労務単価は全国の全職種単純平均で前年度比6・0%の引き上げで、全職種加重平均値は日額2万4852円となった。引き上げは、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った2013年度の改定から13年連続で、過去最高値を更新した。設計労務単価は前年に行った労務費調査結果を前提に決定されるものだが、今回の改定では2月初旬に石破茂首相が中野洋昌国土交通相に引き上げを指示。こうした実質的な引き上げ指示は異例で、労働者の賃上げの流れを加速させたい政府の思惑がうかがえる。
岡山、広島、徳島の3県で8%台に、「東高西低」の傾向が是正
労務単価の前年度比6・0%の伸び率は過去11年で最大で、都道府県別・職種別でみても、1000以上ある単価のすべてがプラスとなった。都道府県別の全職種の上昇率では概ね4~8%の枠内に収まり、大きなばらつきもなく満遍なく引き上げられている。
ただ、全国平均の6・0%を上回る大幅な伸びは西日本地域に集中。西日本地域にある岡山(8・5%)、広島(8・1%)、徳島(8・0%)の3県は8%を超える大幅な伸びとなった。一方、東北や関東、北陸などの東日本地域では4~5%台の上昇に止まった都道県が大半だった。労務単価はこれまで「東高西低」の傾向が見られていたが、今回の改定で一定程度是正された格好となった。
法定福利費相当額の反映など算出手法の変更以前の2012年度単価と比較すると、全国・全職種の単純平均は85・8%上昇となった。公共工事の現場労働者の8割以上を占める12職種(特殊作業員、普通作業員、軽作業員、とび工、鉄筋工、運転手・特殊、同・一般、型枠工、大工、左官、交通誘導警備員A、同B)の全国単純平均は5・6%上昇。日額では3万円を超えたのが鉄筋工と型枠工で、とび工や左官も3万円の大台に迫っている(表1)。
| 職種 | 全国平均値 | 2023年度比 |
|---|---|---|
| 特殊作業員 | 27,035円 | 5.60% |
| 普通作業員 | 22,938円 | 5.30% |
| 軽作業員 | 18,137円 | 6.80% |
| とび工 | 29,748円 | 4.80% |
| 鉄筋工 | 30,071円 | 5.90% |
| 運転手(特殊) | 28,092円 | 5.00% |
| 運転手(一般) | 24,605円 | 5.40% |
| 型枠工 | 30,214円 | 5.10% |
| 大工 | 29,019円 | 6.30% |
| 左官 | 29,351円 | 6.80% |
| 交通誘導警備員A | 17,931円 | 5.70% |
| 交通誘導警備員B | 15,752円 | 5.70% |
上昇率の最小が「普通船員」、最大が「電工」の8・6%
今回と前回のどちらも全都道府県で単価を設定した35職種を見ると、上昇率が平均の6・0%を上回っているのは約3割の10職種。約5割の17職種が5%台の上昇率だった。今回の改定で前回より上昇率が大きかったのは▽軽作業員▽電工▽溶接工▽潜かん世話役▽トンネル世話役▽潜水士▽左官▽配管工▽ガラス工▽ダクト工▽設備機械工-の11職種だった。
前回からの上昇率が最小だったのは「普通船員」の4・4%、最大が「電工」の8・6%。2024年の平均消費者物価指数は前年比2・7%の上昇で、生鮮食品とエネルギーを除いても2・4%の上昇となっており、ほぼ全職種で物価上昇を大幅に超える単価引き上げを実現したことになる。
設計が5・2%、測量が9・3%、地質調査が6・2%
設計業務委託等技術者単価は全職種の単純平均で5・7%の引き上げとなった。労務単価と同様に13年連続の上昇で、過去最高を更新した。全20職種のうち前回から据え置きとなった2職種を除き、すべての単価でプラス改定となった。
業務別の単価上昇率は設計業務(7職種)が平均5・2%、測量業務(5職種)が平均9・3%、航空・船舶関係業務(5職種)が平均3・2%、地質調査業務(3職種)が平均6・2%。職種別でみると、かなりばらつきがあり、全20職種のうち6職種の上昇率は10%を超えた。
時間外労働に伴う割増賃金の算出に用いる「割増対象賃金比」は、測量業務の「測量助手」「測量補助員」、航空・船舶関係の「操縦士」「撮影士」「撮影助手」「測量船操縦士」の計6職種で変更。割増賃金は、各単価を1時間当たりの額に割り戻した上で、時間数と割増対象賃金比を掛けて算出する。
発表後すぐに技能者賃金の「おおむね6%上昇」の申し合わせ
単価設定は、毎年10月に全国各地で実施する公共事業労務費調査で収集した実際の賃金データをもとに決定される。このため、賃金が下落傾向にあると、その低い賃金をもとに翌年の設計労務単価が設定され、デフレスパイラルに陥ると、指摘されてきた。
こうした単価の下落傾向の流れを変えたのが、必要な法定福利費相当額を加算するなどの政策的な措置を行った2013年度の改定だ。それ以降、労務単価も業務委託等技術者単価も上昇を続けている。ただ、前年度比の伸び率が1・0%に止まることもあっただけに、今回の6・0%の伸び率は異例ともいえる。
さらに、設計労務単価が公表された2月14日に石破茂首相など政権幹部と建設業主要4団体による車座対話が首相官邸で開催され、その場で中野洋昌国土交通相と建設業主要4団体が2025年に技能者賃金の「おおむね6%上昇」を目標に官民で取り組むことを申し合わせるなど、異例の早さで技能者の賃上げの流れができあがった。
技能労働者の賃上げを実現できるのか、業界の真価が問われる
石破政権は賃上げ促進を経済政策の柱に掲げており、特に地方経済に大きな影響力を持つ建設業界が積極的に賃上げに動けば、他業界にも波及し、地方経済の活性化につながる可能性もある。国土交通省は新単価が公共工事だけでなく、民間工事でも反映されるよう今後関係機関に要請していく方針で、業界全体に賃上げムードを醸成していく考えだ。
一方、中央建設業審議会(中建審)のワーキンググループでは改正建設業法で規定する「労務費に関する基準(標準労務費)」についての検討を進めている。この中でも設計労務単価を基礎とした労務費の行き渡り策や賃金の支払い方法などが議論されており、設計労務単価が一つの指標になる可能性が高い。今回の大幅な引き上げは政策的な色合いが強いだけに、業界側は現場で働く技能労働者に賃上げという形で今回の単価を行き渡らせなければならない。これまで「設計労務単価は上昇しているが、その実感がない」と嘆きの声を建設技能者からよく聞いた。今回もそうした状況が続くようであれば、業界自体の信用を失うことになりかねない。もちろん、担い手確保もできないだろう。専門工事業者も含め、業界全体がどこまで本気で賃上げに取り組む覚悟があるのか。それが問われている。

執筆者
日刊建設工業新聞社 常務取締役事業本部長
坂川 博志 氏
1963年生まれ。法政大社会学部卒。日刊建設工業新聞社入社。記者としてゼネコンや業界団体、国土交通省などを担当し、2009年に編集局長、2011年取締役編集兼メディア出版担当、2016年取締役名古屋支社長、2020年5月から現職。著書に「建設業はなぜISOが必要なのか」(共著)、「公共工事品確法と総合評価方式」(同)などがある。山口県出身。

PickUp!
建設業の労務費とは?
人件費との違いや計算方法まで徹底解説!










