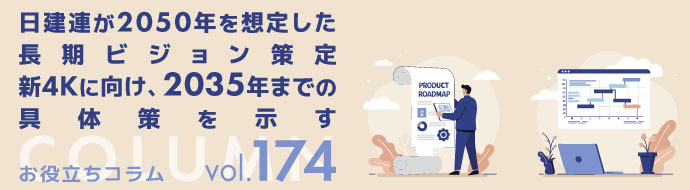
日本建設業連合会(日建連、宮本洋一会長)は7月、建設業全体の中長期的な方向性を示した新しいビジョン「建設業の長期ビジョン2・0-スマートなけんせつのチカラで未来を切り拓く-」を発表した。2035年までの建設市場の規模や担い手数を試算した上で、具体的な方策を提示。主な方策として▽デジタル技術を活用し、2035年の生産性を2025年比で25%向上▽技能労働者の賃金を年平均7%以上継続的に引き上げ、40代で平均年収1000万円超に▽2035年までに全建設現場で「土日祝日(夏季、年末年始休暇を含む)一斉閉所」の実現ーなどで、かなり意欲的な方策が盛り込まれている。その背景には深刻な人手不足による施工能力の減退をどう回避していくのかという危機感がある。ビジョンの内容を紹介する。
35年の建設投資額は84・3兆円、技能労働者が129万人不足
新長期ビジョンは建設業に期待される役割や、あるべき姿を示すことで建設業がさらに進化していくための道筋を示している。2050年を一つ目標として据え、どのような時代なのかを予測。具体的には▽人口減少・高齢化の進展▽デジタル・AI技術の本格展開▽働く場所や時間の多様化▽災害の激甚化▽インフラのリストラクチャリング▽カーボンニュートラルな社会の実現▽グローバル化と国際的な安全保障の複雑化▽宇宙・海底・地底といった人類未踏の領域への挑戦ー8つの項目を挙げ、建設業がその時代に果たす役割を概観した。
2050年の目指すべき方向性を示しつつ、今後10年間の施策が重要になると判断し、2035年までに取り組むべき方策を明記した。まず建設投資額とそれに見合った必要な技能労働者数を試算。2035年の建設投資額を名目で84・3兆円と推計し、必要な技能労働者数を393万人とした。これから10年間、何の施策も実施しなければ技能労働者数は264万人(2025年が299万人)に減少し、129万人が不足すると分析。このギャップを埋めるには、生産性向上と入職者の増加が不可欠になるとした。
今後10年で生産性を25%向上、現場のCO2排出量を60%削減
ビジョンでは、仮に国土交通省が進める「i-Constructios2.0」を実現しても31万人が不足し、日建連が過去10年と同程度の生産性向上を進めても68万人が不足すると指摘。このため、今後10年をかけて生産性を25%高める目標を掲げた。
それを実現するツールとしてBIM/CIM、ドローン、XR(クロスリアリティー)技術、自律型重機、ロボットなどを挙げ、建設現場のスマート化を行い、省人化・省力化を進める。同時にプレキャスト(PCa)やモジュールの規格化、3Dプリンターといった新技術も取り入れ、生産工程全体を見直す。一方、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、施工段階における二酸化炭素(CO2)の排出量を2013年度比で60%削減する目標も盛り込んだ。
多様な人材が活躍できる環境整備も進める。今後10年間は、新成人数が100万人を超えるため、これが最後のチャンスとし、処遇改善や働き方改革などを急ピッチで進め、若年層を惹きつける環境づくりを行う。男女を問わず若者や外国人から選ばれる産業にするため、「異次元の処遇改善」と「人材育成の抜本的強化」、「多様な人材活躍」の3本柱を掲げた。
「土日祝日一斉閉所」を実現、建退共制度で退職金1000万円超え
「異次元の処遇改善」では、技能労働者の所得を倍増させる。全産業平均を圧倒的に上回る水準とするため、年平均7%以上の持続的な賃上げを実施。40代の平均年収を現状の500万円程度から、1000万円超へと引き上げる。
建設業退職金共済(建退共)制度の抜本的改善も検討。現行の単一掛け金制度を改め、建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用したレベル別の掛け金にするとともに、退職金1000万円を超える額を確保する仕組みを構築し、最終的には2000万円も視野に入れる。
働き方・休み方改革に向け、すべての現場を「土日祝日(夏季・年末年始休暇を含む)一斉閉所」とする。猛暑日の作業禁止といった制度改革も進める。休日の増加で収入が減少しないよう技能労働者の「社員化」も推進。多様な働き方・休み方を取り入れ、個人のライフスタイルに合った就労を可能にする一方、勤務体系も見直し、若年層の建設業離れを食い止める。施工能力のない企業による中間搾取を排除するため、行き過ぎた重層下請構造の改善も目指す。
技能者労働育成システムの導入、同一労働同一賃金の原則を徹底
人材育成の抜本的な強化では、技能労働者が体系的に技能が取得できる仕組みとして、「学習」と「実践」を組み合わせた技能者労働育成システムの導入を目指す。ドイツの「アプレンティスシップ制度(見習い制度)」などを参考に、働きながら週末に集中的にOFFーJTを行い、3年程度で技能労働者を育成する教育訓練制度を国と協力しながら整備する。
多様な人材の活躍では女性の活躍をさらに促進させる。女性就業者100万人(うち技能労働者20万人)の目標を掲げ、環境整備や啓発活動を展開する。「けんせつ小町活躍推進計画」が2024年度で終了し、2025年度に新しい計画が始動。2035年度に会員企業の女性技術者比率(2023年度8%)と女性管理職比率(3・5%)を、2023年度比で倍に引き上げる。
外国人労働者の確保も重要となる。技能実習制度に代わる「育成就労制度」(2027年度からスタート)などを活用し、外国人からも選ばれる産業へと変革する。厚生労働省がまとめた外国人雇用状況によると、2024年10月末時点の建設業の外国人労働者は前年比22・7%増の17万7902人。増加率は2年連続して20%を超えた。外国人雇用事業所は13・7%増の4万4811カ所で、すでに建設労働者の7・7%、事業所の13・1%を占めている。
外国人材の働きやすい環境づくりには国や業界団体などが連携して、日本語教育や技能習得を支援する取り組みを推進する必要がある。いまや建設業界は外国人材抜きでは成り立たないところまできている。業界挙げて同一労働同一賃金の原則を徹底し、「安い労働力」「繁閑調整の労働力」といった考え方を捨て、新たな戦力としてどうキャリアパスを整備できるかが重要になる。
技能労働者だけでなく、建設技術者も同様の課題を抱える。工学部や高専への入学者数が減少し続けており、特に土木・建築系の学生数が落ち込んでいる。産学官の連携によって進路誘導や教育支援を強化し、建設業界の裾野を広げていく。
「共利」を実現し、この10年間で新4Kをどう実現していくのか
ビジョンでは「すべてのサプライチェーンにおけるWin-Win関係の構築」と「常に推進すべきこと」も盛り込まれている。長年の慣習とも言える受・発注者間の片務性を払拭し、発注者・受注者双方に意識改革と行動変容を促す方策を提示。建設プロジェクトに関わる全ての関係者がWin-Win、つまり「共利」の実現を訴えている。
一方、各企業の持続性を担保するため▽コンプライアンスの徹底▽安全対策の徹底▽建設業の魅力の発信-も掲げている。発注者だけでなく、従業員、一般消費者、行政、投資家、地域住民などすべてのステークホルダーの信頼を得ていなければ、建設企業は成り立たないとし、発注者との片務性を解消するためにも、自らが信頼される企業であることを示す必要があるとしている。
今回のビジョンから見てきたものは、建設業界が抱える課題への強い危機感。その最大の課題は人材不足による施工能力の減退と言えるだろう。自社の建設技術者だけではなく、現場の第一線で働く技能労働者をどう確保していくのか。これまでの3K(きつい、汚い危険)のイメージを払拭し、どう新4K(給与が良い、休暇が取れる、希望が持てる、かっこいい)を実現し、建設業界で働く人を増やしていくのか。ビジョンで指摘するように、この10年が確かに正念場になることは間違いない。

執筆者
日刊建設工業新聞社 専務取締役事業本部長
坂川 博志 氏
1963年生まれ。法政大社会学部卒。日刊建設工業新聞社入社。記者としてゼネコンや業界団体、国土交通省などを担当し、2009年に編集局長、2011年取締役編集兼メディア出版担当、2016年取締役名古屋支社長、2020年5月常務取締役事業本部長を経て、2025年4月から現職。著書に「建設業はなぜISOが必要なのか」(共著)、「公共工事品確法と総合評価方式」(同)などがある。山口県出身。

「2025年の崖」対策は万全ですか?
建設業界のDX事例










