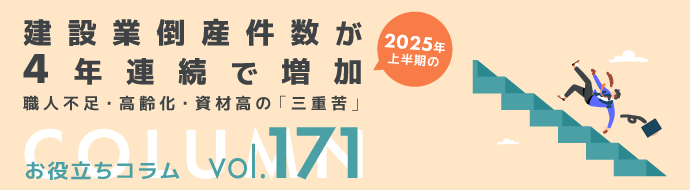
帝国データバンクが発表した2025年上半期(1~6月期)の建設業の倒産動向によると、建設業の倒産件数は986件で、前年同期に比べ69件増加した。上半期でみると、4年連続の増加で過去10年で最多を更新。通年で2000件台に達する可能性もあるという。2024年度の建設投資額は前年度比3・6%増の73兆6400億円と好調を維持しているにも関わらず、なぜ倒産件数は増えているのか。高騰した資材価格の転嫁が思うようにできなかったことや、職人などの人手不足が影響していることが背景にある。
物価高に起因する倒産が最多の12%を占める
帝国データバンクの調査によると、負債1000万円以上、法的整理による、2025年上半期倒産件数は前年同期比7・5%増の986件となった。倒産の要因では、全体のうち12・0%に相当する118件が「物価高」に起因するもの。同社によると、鉄骨や木材、住設機器など建設資機材の価格が高騰し、それを価格転嫁できず、事業継続を断念したケースが多くみられたという。
一方、経営トップの後継者が決まらず事業が引き継げない「後継者難」を要因とした倒産が全体の7・0%に当たる69件。次いで職人などの「人手不足」を要因とした倒産が54件あり、全体の5・5%を占めた。いずれの要因も2018年以降の上半期ベースで最多となっている。
今回の発表資料には、工種別の倒産件数が掲載されていないため、総合工事業の倒産が多いのか、専門工事業の倒産が多いのかなどは分からない。ただ、2024年の建設業の倒産データでは、倒産件数1890件のうち、鉄筋や大工、とびなどの「職別工事」企業が879件と最も多く、土木・建築工事などの「総合工事」企業が600件、電気・管工事など「設備工事」企業が411件となっている。いずれの件数も前年を上回り、特に「職別工事」「設備工事」は過去10年で最多となっている。
一方、企業の規模別では従業員数が「10人未満」が1742件で全体92・2%を占め、「10人以上50人未満」が143件、「50人以上100人未満」が5件で続いた。「100人以上」は2年連続で発生しておらず、小規模事業者が大半を占めた。
こうしたデータを見る限り、受注量の減少に伴う「不景気型」倒産ではなく、経営基盤が脆弱な中小・零細企業が積算の甘さに伴う「物価高への対応の失敗」や、人材不足による「施工能力の低下」が、倒産の引き金となっていそうだ。
改正建設業法で設計変更協議の門前払いは禁止
では、こうした物価高対策や人材不足対策にどう向き合えば良いのか。価格転嫁について公共工事の場合、スライド条項などを積極的に活用し、価格転嫁を確実に進めることが重要となる。ただ、国発注の直轄工事ではスライド条項の適用が円滑に行われているが、一部の地方自治体では未だに設計変更自体に難色を示す自治体もあると言われており、すべての公的発注機関に対しスライド条項の適正な運用が求られる。
これまで設計変更が難しいと言われていた民間工事も、2024年6月に成立した「第三次担い手3法(改正建設業法、改正公共工事入札契約適正化法、改正公共工事品質確保法)」で、契約後に急激な資材価格高騰などがあった場合、受発注者間で協議する場を設けることが盛り込まれ、その運用が開始されている。
この規定が盛り込まれた改正建設業法は2024年12月に施行されており、受注者は注文者に資材高騰などの「恐れ(リスク)情報」を事前通知し、その情報に基づき契約変更の協議を受注者が申し出た場合、注文者は協議の場の設定について門前払いはできなくなっている。違反企業は行政指導の対象となる。
民間同士の請負契約では、これまで6割近くが請負代金などの変更規定がなかったと言われている。施行後は契約書に「変更額を協議して定める」といった記載が必須となっており、実際に設計変更されるかどうか個別の協議に委ねられるが、少なくとも注文者は受注者から協議の申し入れがあれば、応じなければならない状況になっている。
これは発注者と元請企業間の契約だけでなく、元請企業と下請企業間の契約にも適用される。それだけに中小・零細企業も一次下請企業らとの契約は口頭ではなく、書面で契約することが重要となっている。必要があれば「リスク情報」も事前に通知することも考えられる。インフレは今後も続く可能性が高いだけに、事前に価格転嫁の策を練っておくことも必要だろう。
休日と給与の増加を同時に進めることの難しさ
一方、人材不足対策は社員や職人の処遇改善と、外国人材の活用が重要になる。2024年4月に時間外労働の上限規制が建設業にも適用され、建設現場でも徐々に週休2日制が進みつつある。ただ、現場で働く建設技能者からは休暇は増えたが、給与は減ったという声も漏れる。建設技能者は出来高払い制や日給月給制が未だに採用されているケースが多く、働く日数・時間が減れば給与も自動的に下がってしまう。
国土交通省はこうした事態を踏まえ、改正建設業法で慢性的な人手不足に陥っている建設技能者の労務費の確保に向けた新たな仕組みを盛り込んだ。具体的には中央建設業審議会で建設技能者の「労務費に関する基準(標準労務費)」の作成を行い、その標準労務費を大きく下回る見積もり・契約の禁止や、価格転嫁協議の円滑化、工期ダンピング対策の強化などの措置を新たに講じるとした。
国土交通省は現在、この標準労務費の作成作業を進めており、先行する鉄筋や型枠大工では公共工事設計労務単価をベースとした標準労務費が固まりつつある。ただ、こうした方策は、労働時間を減らす一方で、働く人たちの給与も増やすという、相反した関係にあり、これを進めるためには建設費全体を高くしていかなければならない。建設費の高騰は工事着工の中止や延期などを招く可能性もあり、市場が急激に低迷することも考えられる。そのためにも建設市場を下支えする、安定的な公共事業量の確保が必要だろう。
市場が活況の時に人材・設備の投資に取り組む
先日、ある鉄筋工事会社が高卒の初任給(手当含む)を30万円以上にしたという記事を読んだ。優れた人材を確保するには、給与の大幅アップは避けられないという判断なのだろう。ただ、多くの専門工事業は思うように日本人の人材を確保できず、施工能力を担保するには外国人材に頼らざるを得ない状況だ。
建設分野で活躍する外国人技能者はいまや、建設技能者全体の約4・9%に当たる約14・6万人(2024年12月末時点)にも達する。特定技能制度の活用も進み、認定者数は1号が4万240人、2号が290人(いずれも2025年2月末時点)にもなる。こうした外国人材も日本人と同様な処遇にし、重要な戦力として育成することが大切だ。
いずれにせよ、建設市場がある程度活況でなければ、人材への投資ができない。7月に建設経済研究所と経済調査会が発表した建設投資予測(名目値)では、2024年度は前年度比3・6%増の73兆6400億円(実績)、2025年度は同2・5%増の75兆4500億円、2026年度は同5・0%増の79兆2100億円を予測している。
この投資予測を見る限り、工事量は微増で推移しており、いまこそ人材や設備に投資するチャンスとも言える。人材だけでなく、生産性の向上に向けて機械化や自動化などの投資にも積極的に取り組む必要もあるだろう。ICT技術を取り入れ、できるだけ省人化を進める。こうした積極的な投資が倒産リスクを回避する一助にもなるだろう。

執筆者
日刊建設工業新聞社 専務取締役事業本部長
坂川 博志 氏
1963年生まれ。法政大社会学部卒。日刊建設工業新聞社入社。記者としてゼネコンや業界団体、国土交通省などを担当し、2009年に編集局長、2011年取締役編集兼メディア出版担当、2016年取締役名古屋支社長、2020年5月常務取締役事業本部長を経て、2025年4月から現職。著書に「建設業はなぜISOが必要なのか」(共著)、「公共工事品確法と総合評価方式」(同)などがある。山口県出身。

PickUp!
建設業界の最新動向2025
~市場概況、制度改正、建設コストの値動きまで~










