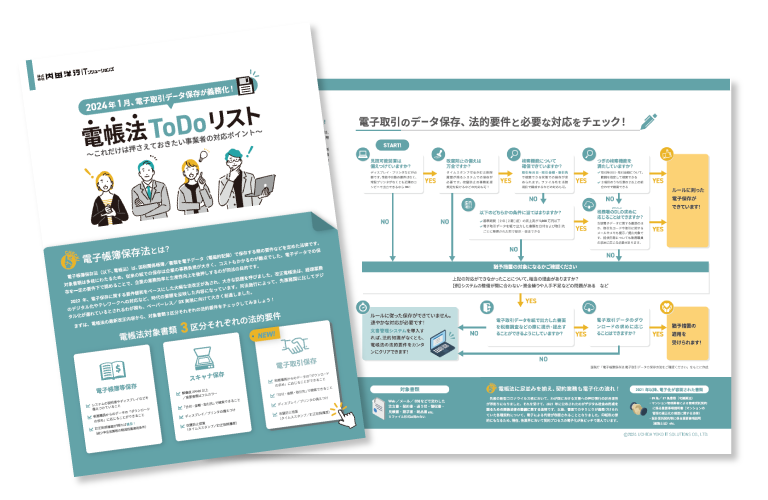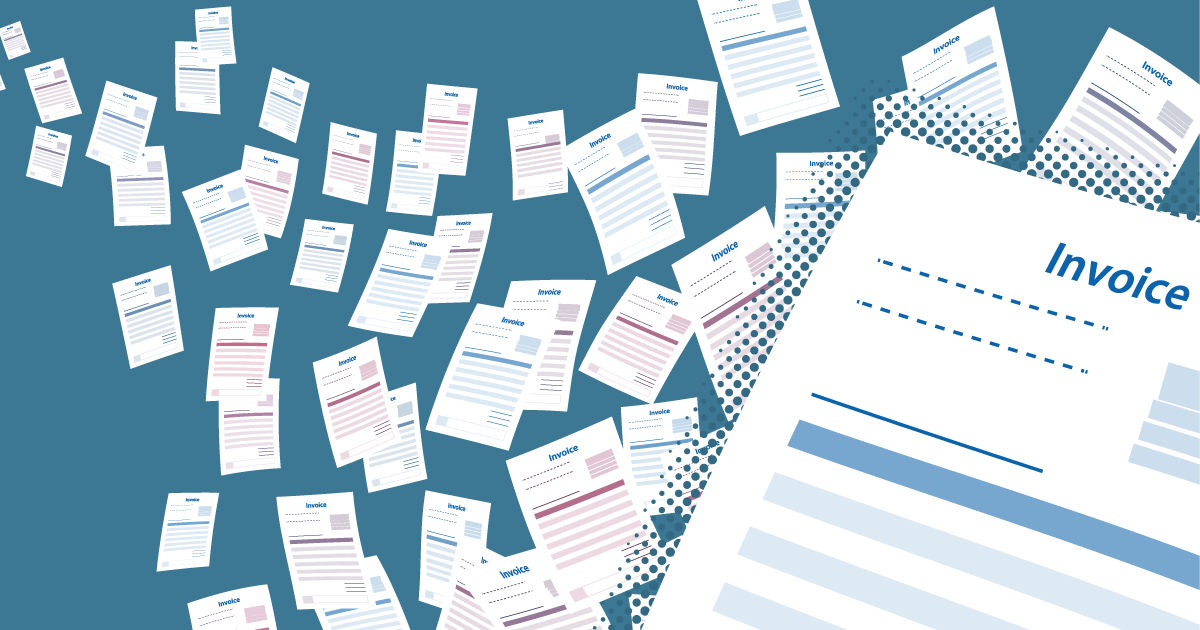DXの第一歩、電子帳簿保存法対応
改正電帳法の宥恕期間が予定どおり明け、2024年1月より、電子取引の電子データ保存が義務化されています。近年、工事請負契約の電子化が進む建設業では、特に大きな関心事といえるのではないでしょうか? 業務効率化や税制面のメリット/デメリットを考えれば、早めの対応は必須です。本稿では、改正の概要から注意点、対応策までをわかりやすくまとめました。
CONTENTS
01.電子帳簿保存法とは?
02.電帳法2022の改正点
1)電子帳簿等保存法
2)スキャナ保存
3)電子取引のデータ保存
03.おススメのソリューション
04.よくある質問
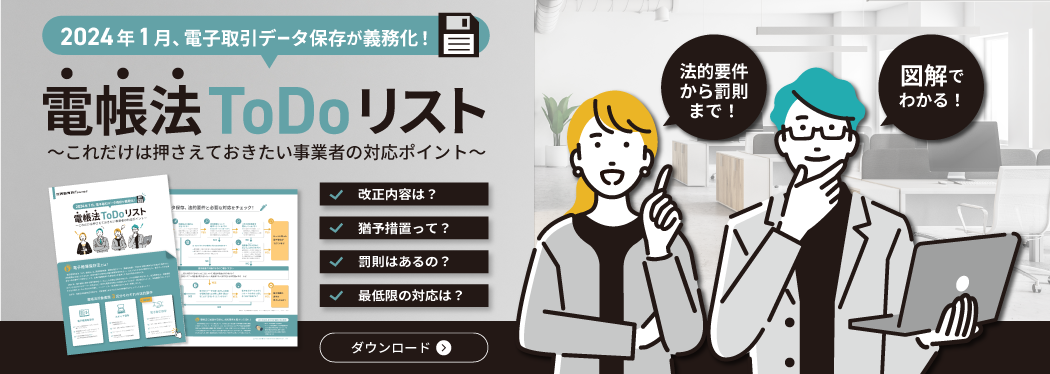
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法(以下、電帳法)をひとことでいえば、従来、紙での保存が義務づけられていた国税関係帳簿書類について、電磁的記録(電子データ)による保存を認めた法律です(第4条)。
事務従事者の負担軽減、紙保管のスペースやコスト削減が図れるため、事業者さまにとっては、歓迎すべき法律といえるでしょう。
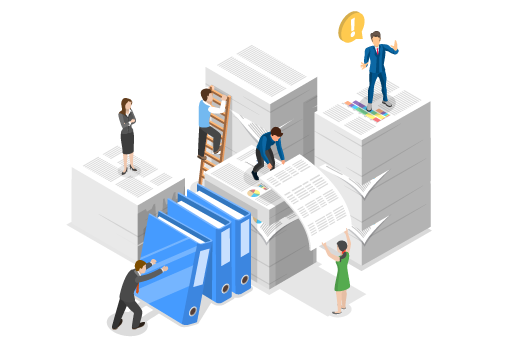
ただ、煩雑な帳票類を電子データで保存して管理することは、大幅な業務効率化に繋がる一方、不正な複製・金額の編集など、改竄リスクが伴います。利便性の追求と真実性の担保はトレードオフの関係にあることはいうまでもありません。同法は、そのバランス調整を図るために、保存要件について細かく定めています。
1998年に施行されて以後、保存要件については何度も見直されてきましたが、2022年の法改正は特に大きな転換点といえるでしょう。単なる時代に沿ったアップデートというだけでなく、国を挙げてのペーパーレス化、DXの促進を積極的に目指した内容になっているからです。
電帳法2022の改正点
電帳法でいう電子データは、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3つの区分に分類されます(図1)。
2022年の改正内容について、区分ごとにおさらいしていきましょう。
1)電子帳簿等保存
同法では、会計ソフトなどで作成した電子帳簿データがあれば紙の帳簿に代えられる旨が定められています。2022年の改正法では、これまで必要だった税務署長の事前承認が不要になりました。
また、これまでは複雑な検索要件が課されていましたが、改正後の要件は取引年月日と金額、取引先のみとなり、大幅に緩和されています。

2)スキャナ保存
緩和の流れは電子帳簿同様
同法では、取引先から受け取った請求書や見積書など紙の書類についてスキャン文書での保存(解像度200dpi以上)が認められています。さらに、2016年にはデジタルカメラやスマートフォンで撮影した画像データも容認されました。
2022年の法改正では、電子帳簿同様、税務署長の事前承認が廃止に。これにより、紙の原本については即廃棄することができるようになりました。
同じく検索要件も緩和されていますが、スキャナ保存データで検索要件を満たすには、ファイル名を取引年月日・金額・取引先名で構成するなどの工夫が必要でしょう。もちろん、OCR機能を持ったシステムがあれば最も簡便です。
タイムスタンプ要件が不要に
それらに加えて、スキャナ保存ではタイムスタンプ要件についても緩和されています。
タイムスタンプとは?
TSA(Time Stamping Authority;時刻認証局)の発行する時刻情報を付与することで電子データ化された日時を証明、改竄が行われていない原本性を担保する仕組み。
スキャナ保存する際、これまでは書類の作成・受領から遅滞なくデータ化してタイムスタンプを押す必要がありました。2022年の改正法では、この保存までの期間が最長2カ月+7営業日(約70日)以内に伸長され、受領者のサインも不要になっています。
なお、訂正・削除履歴が残るクラウドシステムに格納する場合、タイムスタンプ自体が不要になるため、業務効率の大幅改善が期待できます。
3)電子取引のデータ保存
今回の法改正で、多くの事業者さまにとって特に大きな関心事は、電子取引に関する改正ではないでしょうか。具体的にいえば、メールやクラウド、アプリ、EDI、USBメモリなどを介した注文書、契約書、送り状、領収書など書類のやりとりについて(第2条)、今後は大きく様変わりします。

紙媒体での保存が不可に
これまで電子取引情報の保存については、①電子データ、②COM(電子計算機出力マイクロフィルム)、③紙媒体の書面のいずれかを選択できました。
2022年以降は②と③が廃止され、電子データへの一本化が義務づけられます。
建設業には大きなメリット
巨額が行き来する建設業では、当然、紙の契約書を交わすたびに発生する印紙税も大きくなります。電子契約に切り替えれば印紙税が発生しないため、大きなタックスメリットになるでしょう(参考記事:建設業こそ電子契約を導入すべき3つの理由【2023最新】)。
クラウドシステムを利用すればタイムスタンプが不要になるほか、テレワーク対応や災害時のデータバックアップが図れるなど、業務効率化やBCPの面でも利点があります(参考記事:2022年、建設需要のトレンドは“防災”へ 問われる建設業のBCP)。
猶予措置があるも油断は禁物
3区分のうち、この電子取引データの電子保存については、事業者の即応が難しいことが予想されたため、2年の宥恕期間が設けられました。ただ、その宥恕期間も2023年で予定どおり終了しており、2024年1月以降は全事業者に対応が義務づけられています。やむを得ない事情がある場合に限り、新たに猶予措置の適用が認められるものの、いずれ対応しなければならないなら補助金を活用できるいまから準備を進めるのが賢明です。

PickUp!
【2023最新版】建設業向け!
オススメ補助金/助成金6選
| 電子帳簿保存 | スキャナ保存 | 税務署長の事前承認 | 必要 | 廃止 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子取引 | 検索要件 |
①取引年月日、金額、取引先 ②日付・金額に係る記録項目について範囲指定 ③二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること |
大幅緩和 取引年月日・金額・取引先のみ |
||
| タイムスタンプ要件 | ・遅滞なく付与 (重要書類で受領後3営業日以内) |
緩和 ・最長2カ月+7営業日(約70日)以内 ・受領者のサイン不要 大幅緩和! |
|||
| 紙出力 | 可 | 不可 ※2023年12月末まで猶予あり |
|||
おススメのソリューション
国税関係帳簿書類の電子保存について、細かなルールを定めた電子帳簿保存法。保存要件を満たさなかった場合、青色申告が取り消されることもあり、控除や経費が認められなくなります。また、10%の重加算税が課される罰則も新設されており、細心の注意が求められるでしょう。
ただ、電帳法の保存要件は難解で、苦慮されている事業者さまも多いのではないでしょうか? 内田洋行ITソリューションズでは、そうした事業者さま向けにクラウド型のERPシステム「PROCES.S」をご案内しています。
同システムはJIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)による電子帳簿ソフト法的要件認証を受けており、担当者さまが電帳法について深く把握していなくても、法令に準拠した業務遂行が可能です(※2023年、インボイス制度にも対応!)
改正電帳法への事業者の対応をわかりやすく図説した資料と、改正電帳法に対応した「PROCES.Sユクタスドキュメント連携オプション」の製品カタログをご案内しています。どちらも無料でダウンロードいただけますので、ぜひこちらもご活用ください!
よくある質問
- Q帳簿や書類等の電子保存について、電帳法以外でも考慮すべき法律はありますか?
- A建設業扱う膨大な書類の保存については、電帳法以外でも建設業法や大気汚染法などさまざまな法律にまたがって細かな定めがあります。法律によって保存すべき書類や保存期間に差異がありますので、併せてチェックしておいた方がよいでしょう。
- Q保存すべき書類や保存期間について、建設業法ではどう定められていますか?
- A建設業法第40条3では、営業に関する帳簿の備えつけ/図書(完成図など)の保存について定められています。保存期間は前者が5年、図書に関しては10年です。
本記事の関連記事はこちら
・国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」
・国税庁「電子帳簿保存法一問一答 【スキャナ保存関係】」
・国税庁「電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】」
・国税庁「はじめませんか、書類のスキャナ保存」
・経済産業省「どうすればいいの?「電子帳簿保存法」」
・公益社団法人日本文書情報マネジメント協会「JIIMA認証制度」