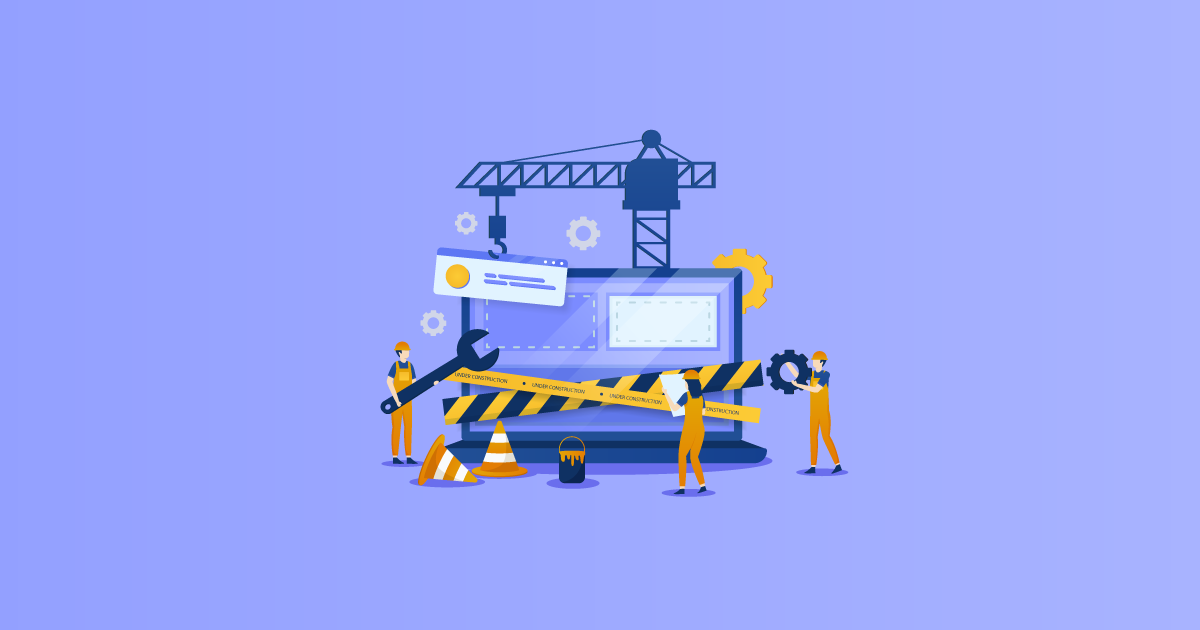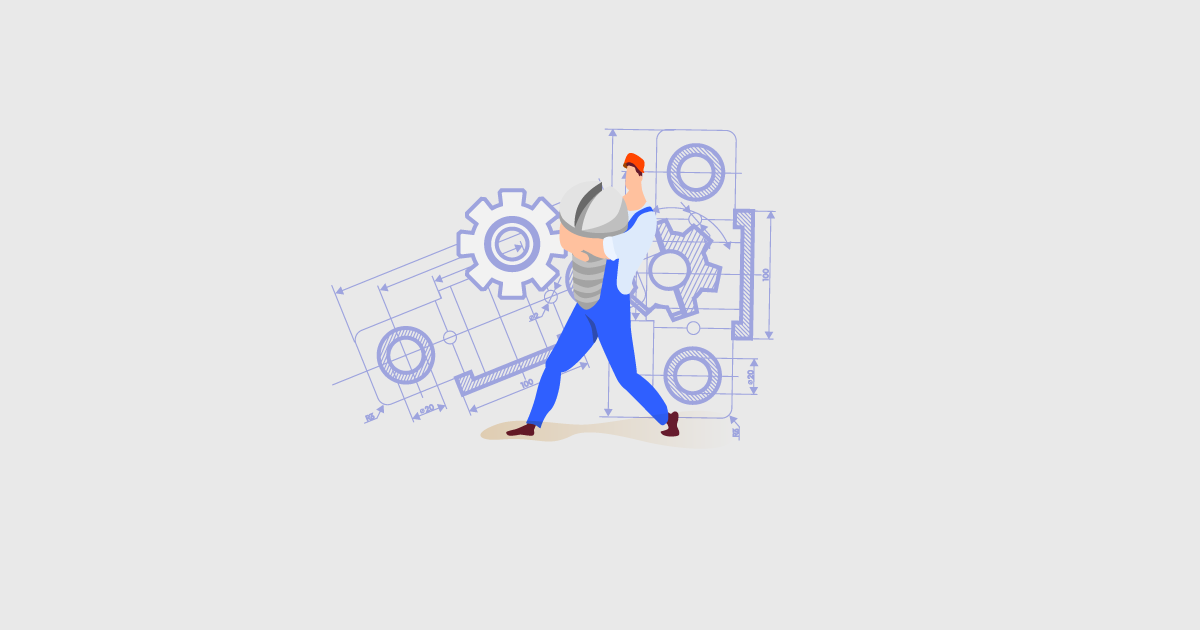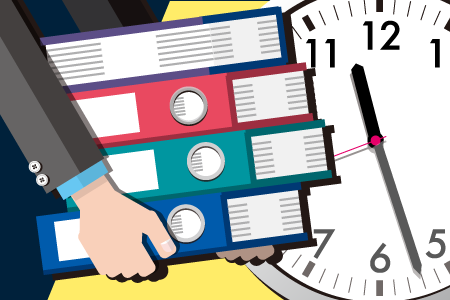建設業の強い味方、補助金/助成金を一挙紹介
前回の記事でお伝えしたように、2024年問題を受けた建設業の人手不足と材料費の高騰は急加速しています。建設業は、資金繰りと人手不足解消のためのDXを両立させなければならない、きわめて困難な立場に置かれています。そこで積極的に活用したいのが、国からの救済措置ともいうべき補助金・助成金です。本稿では、数ある補助金・助成金のなかから、建設業事業者さまが特に活用しやすいものを7つ、厳選してご紹介します!
CONTENTS
01.補助金/助成金とは?
02.建設業こそ補助金/助成金活用を検討すべき理由
03.建設業向けオススメ補助金/助成金7選
04.建設業の補助金活用事例集
05.よくある質問

補助金/助成金とは?
補助金と助成金は、いずれも国が推進する政策に賛同して活動する事業者を支援するために交付されるお金です。企業の資金調達において主な手段となる融資とは異なり、返済の必要がないという大きなメリットがあります。
厳密な定義はないにせよ、一般的な傾向として、補助金と助成金は次項のように大別されます。理解を深めるために、まずは両者の違いについて整理してみましょう。
補助金と助成金の違い
補助金と助成金では、まず、それぞれの管轄と財源が違います。
IT導入補助金に代表される補助金の管轄は、多くの場合、経済産業省(※中小企業庁は経産省の外局)か自治体で、財源は税金です。
一方、雇用関係の取組みに対して交付される助成金のほとんどは厚生労働省の管轄で、財源は雇用保険料になります。※稀に自治体主催のものもあります。
| 補助金 | 助成金 | |
|---|---|---|
| 管轄 | 経済産業省 (中小企業庁) |
厚生労働省 |
| 財源 | 税金 | 雇用保険料 |
| 交付 | 審査次第 | 条件をみたせば必ず交付 |
| 募集 | 公募期間がある | 通年 |
その他の違いも含めて別表にまとめていますので、そちらもご確認ください。
複数の補助金を併用できるのか?
同一の事業者が複数の補助金を併用する、といったことももちろん可能であり、その旨は多くの補助金公式サイトにも明記されています。ただし、同一事業で複数の補助金を受けることはできません。同一の事業者が複数の補助金を併用する場合、内容が異なる別の事業であることが要件となります。
例を挙げれば、不動産事業者A社がクラウド型ERPを導入する際にIT導入補助金の交付を受け、同時にノウハウを活かして建設業に事業転換し、事業再構築補助金の交付を受ける――といったことは可能です。
申請方法は?
補助金や助成金の申請には、デジタル庁が運営する共通認証システムgBizID(ジービズアイディー)を使います。ひとつのアカウントから、補助金/助成金のほかさまざまな行政サービスへの電子申請が可能となります。
同サービスは無料で使うことができ、発行も簡単。ぜひ、この機会に登録をご検討されては如何でしょうか。
補助金/助成金の注意点
補助金や助成金の交付時期はまちまちですが、いずれも事業に対して後払いであることは注意点といえます。申請/承認から一年後に交付といったスケジュールのものも多いため、急場しのぎの活用には向きません。キャッシュフローに余裕を持った申請が大前提となります。
建設業こそ補助金/助成金活用を検討すべき理由

2025年は建設業にとって大きなターニングポイント
上記の事情に加え、多くの建設業事業者さまにとって、2025年はきわめて重大な局面です。ご存知のとおり、2024年4月より建設業でも時間外労働の罰則付き上限規制が始まりました。いわゆる2024年問題です。
支援制度の活用は不可欠
今後、建設業を取り巻く状況は、これまで以上に過酷になることは疑う余地がありません(参考記事:建設業界の最新動向2025 ~市場概況、制度改正、建設コストの値動きまで~)。そうした状況を踏まえ、政府は補助金/助成金に、多くの予算を割いています。どんな補助金/助成金があるのか? それらを如何に上手に活用するか? 2025年の建設業事業者にとって、必須の知識となることは請け合いです。
特に補助金は、交付を受けるために審査を通過し採択される必要があり、建設現場向きのものやバックオフィス向きのものと傾向が明確に分かれています。それぞれの補助金の特性と採択実績を押さえることは、審査通過するうえでまず必須のポイントです。
補助金/助成金はメリットが大きい
さまざまな外部要因によって業況が悪化した際、事業者の資金繰りを救済するための支援制度は数多くあります。新型コロナ禍の際などは、日本政策金融金庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付に代表される無利子・無担保のゼロゼロ融資に助けられた事業者さまも多くおられるのではないでしょうか。
ただ、無利子・無担保とはいえ、融資を受ければ当然、返済の義務が生じます。すでに述べたとおり、補助金や助成金の最も大きなメリットは、融資制度と異なり返済不要ということです。これを活用しない手はありません。
特に助成金は、審査を通過して採択される必要がある補助金と違い、条件さえ満たせば必ず交付されます。あとでご紹介するように、建設業向けにも多くの助成金が用意されていますので、条件を満たしているなら申請しないのは大きな機会損失といえるでしょう。
建設業向けオススメ補助金/助成金7選
では、さっそく建設業事業者さま向けに厳選した注目の補助金/助成金を7つ、順にご紹介します。
1.IT導入補助金
IT導入補助金とは?
| 通常枠 | 課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助 |
|---|---|
| インボイス枠(インボイス対応類型) | インボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」機能を有するソフトウェアなどを導入するための経費の一部を補助 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 取引関係における発注者がインボイス制度対応の受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業・小規模事業者等に対して当該ITツールを供与する場合に経費の一部を補助 |
| セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃のリスク低減を図る取組みを補助 |
建設業での採択事例
もともと建設業は紙依存の傾向が強い業界で、デジタル化については、他業界に比して大きな遅れがありました。ただ、深刻な人手不足や労働環境の問題から、近年、急速にDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が訪れています。採択事例に建設業事業者さまが数多く名を連ねていることからも明らかです。
具体的には、業界特有の経理会計の複雑さ、現場に出入りする労働者の多さといった問題を受けて、クラウド型原価管理システムや積算システム、勤怠・労務管理システム導入などの採択事例が目立ちます。
その他、ERP導入によって会計管理や原価管理などの基幹業務のデータを一元管理し、劇的に業務効率を改善した事例も数多くあります。IT導入補助金を活用した建設業のERP導入事例をまとめた資料については、バナーリンクからご覧ください。
IT導入補助金まとめ
| 主催 | 中小企業庁 |
|---|---|
| 主な要件 | ITツールの導入による業務効率化 |
| 建設業での活用事例 | 原価管理・労務管理・会計など、バックオフィスの事例が多い |
| 補助額 | ~450万円 |
| 交付申請期間 | 2025年3月31日(月)受付開始(予定)~終了時期は後日案内予定 |
2.建設市場整備推進事業費補助金
建設市場整備推進事業費補助金とは?
つぎに紹介するのは、2025年(令和7年)、建設業向けに新設された注目の補助金、建設市場整備推進事業費補助金です。建設市場整備推進事業費補助金は、地域の守り手となる建設業のICT活用を促進し、発災時の応急復旧対応力の強化や建設現場における生産性向上に資することを目的としています。
補助対象事業は、建設業に係る発災時の応急復旧を想定した防災訓練に際し、作業員の技術習得及び発災時における対応体制の強化による安全性の向上に資するICT機器の導入、並びに発災時以外も含めた建設現場における生産性向上を目的とするICT機器の活用などに関する取組みとなっています。補助上限額は2億4,955万円と非常に高額です。
建設業での採択事例
令和7年に新設された補助金であるため、採択事例についての情報はまだありません。ただ、対象機器としてはウェアラブルカメラやドローン、四足歩行ロボットなどが挙げられています。
建設市場整備推進事業費補助金まとめ
| 主催 | 国土交通省 |
|---|---|
| 主な要件 | 災害対策基本法第39条第1項に基づく防災業務計画において、被災地の迅速な応急復旧活動及び現場の安全確保に資するため、ICT機器を活用した防災訓練等を実施する計画を有すること |
| 建設業での活用事例 | 新設であるため現在不明 ただ、対象機器としてウェアラブルカメラやドローン、四足歩行ロボットなどが想定されている |
| 補助額 | 上限額2億4,955万円(補助率は原則1/2) |
| 交付申請期間 | 2025年2月13日(木)~2月25日(火)17時まで |
3.事業再構築補助金
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金は、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行なう事業者を重点的に支援する補助金です。ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化またはこれらの取組みを通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
申請枠によるものの、令和5年度の最大補助額が5億円とその高額さから耳目を集めた本制度。令和7年度での最大補助額はGX進出類型の1.5億円と減少しているものの、それでも非常に高額であることに変わりありません。
建設業での採択事例
事業再構築補助金の審査項目としては、先端的なデジタル技術や低炭素技術の活用が明記されており、第8回での採択事例に目を通すと、AI搭載建機やドローンを活用した測量など、現場での大胆なICT導入事例が目立ちます。また、建機の電化や建設発生土のリサイクル促進など、SDGsに配慮した取組みも好評価であったことがわかります。
事業再構築補助金まとめ
| 主催 | 中小企業庁 |
|---|---|
| 主な要件 | 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること |
| 建設業での活用事例 | 現場でのICT化やSDGsを意識した取組みの事例が多い |
| 補助額 | 1,500万~1.5億円 |
| 交付申請期間 | 第13回は2025年1月10日(金)~3月26日(水) |
4.ものづくり補助金
ものづくり補助金とは?
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入と、近年続くさまざまな制度変更への対応は、多くの中小企業にとって大きな負担です。もともと労働時間が長時間化しやすく、一人親方問題など業界特有の問題を抱えがちな建設業では、その影響はなおさら深刻といえるでしょう。
そうした業況への救済措置として、中小企業・小規模事業者等が取組む革新的サービス/試作品開発・生産プロセスの改善など、生産性を向上させるための設備投資を支援する制度が、ものづくり補助金です。
ものづくり補助金も補助額が100万~3,000万円と非常に高額であり(最大3,000万円はグローバル枠)、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例措置もあります。
補助対象は、積極的な賃上げや付加価値額増大に取組む中小企業・小規模事業者等です。
ものづくり補助金の基本要件
事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を 3.0%以上増加させる。
事業計画期間において、従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させる。
事業計画期間において、事業所内最低賃金を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円以上高い水準にする。
「次世代育成支援対策推進法」第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行う
建設業での採択事例
建設業事業者の採択実績も数多くあり、代表的なものでは、ICT搭載建機やドローン、3Dレーザースキャナ導入による現場での業務効率改善などが挙げられます。ざっくりとバックオフィス向けのソフト面であればIT導入補助金、建設現場でのハード面であればものづくり補助金の範疇と考えればよいでしょう。
ものづくり補助金まとめ
| 主催 | 中小企業庁 |
|---|---|
| 主な要件 | 積極的な賃上げ等 |
| 建設業での活用事例 | 建設工事に用いるICT搭載建機や三次元測量など、現場での生産プロセスにかかわる事例が多い |
| 補助額 | 100万~3,000万円(大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例有) |
| 交付申請期間 | 第19次は2025年4月11日(金)17:00 申請受付開始~~4月25日(金)17:00 |
5.働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
働き方改革推進支援助成金とは?
ご存知のように、2023年4月から中小企業でも時間外労働の割増賃金増額が適用されており、人手不足に悩む中小企業にとっては、看過できない大きなコスト要因となっています。そうした事情を鑑み、厚労省は労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業を支援する制度を併せて設けました。それが働き方改革推進支援助成金です(参考記事:2023年4月、割増賃金引き上げへ! 事業者が対応すべき3つのポイント)。
2024年4月より時間外労働の罰則付き上限規制も始まった建設業とは、特に相性のいい助成金です。
建設業での活用例
労働時間の削減には、まず、従業員の労働時間を正確に把握することが不可欠です。ただ、現場に多くの労働者が出入りする建設業では、労務管理は煩雑になりがちで、けっして容易ではありません。
建設業での同助成金の活用例としては、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新などが考えられます。いずれも助成金の対象経費です。
働き方改革推進支援助成金まとめ
| 主催 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 主な要件 | 時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組むこと |
| 建設業での活用例 | 労務管理用ソフトウェア導入など |
| 補助額 | 最大730万円 |
| 交付申請締切 | 2024年度の交付申請受付は2024年11月29日で終了、2025年の日程は現在不明 |
6.人材確保等支援助成金 & 7.トライアル雇用助成金
建設業における女性労働者確保に向けた取組み

もともと男性の職場というイメージが強かった建設業ですが、2014年(平成26年)に国土交通省がもっと女性が活躍できる建設業行動計画を策定して以後、官民挙げて女性の積極採用が進められています。2020年(令和2年)には、後継となる女性の定着促進に向けた建設産業行動計画が策定、引き続き、業界における多様性の確保をめざしている最中です。
国土交通省の統計から推計すると、建設業における女性比率は約13%。現場作業に携わる数は、当然ながらもっと低くなります。一方で、女性技術者数は、2014年の1.1万人から2018年には1.8万人へと1.64倍に、女性技能者は8.7万人から10.4万人へと1.19倍に増加しており、取組みのたしかな成果が窺えます。
技術者と技能者の違い
建設業において、技術者とは監理技術者や主任技術者といった現場管理者のことです。対して、技能者は実際に現場で作業をする職人を指します。
そうした取組みを支えるべく、建設業の女性入職者増加と定着をめざした助成金が用意されています。その代表が人材確保等支援助成金とトライアル雇用助成金です。
人材確保等支援助成金――若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
労働環境の改善を図り、人材確保と定着をめざす事業主を助成する制度です。ご存知のように、建設業では現場労働者の高齢化・新規入職者の減少が深刻な問題となっており、若年者や女性労働者の受け入れ態勢を整えることは喫緊の課題とされています。
そのために期待されている制度が、同助成金です。助成対象としては、現場見学会やインターンシップ、研修あるいは教育訓練などが挙げられます。
トライアル雇用助成金――若年・女性建設労働者トライアルコース
トライアル雇用助成金は、職業経験の乏しさから安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により一定期間、事業者が試行雇用した際に支給されるものです。求職/求人者の相互理解を促進することで、雇用機会の創出を図ることを目的としています。
35歳未満の若年層、あるいは女性を対象として試行雇用を行った場合、1人あたり最大4万円/月×3カ月がトライアル雇用助成金に上乗せされます。
いずれの助成金も、提出期限・記入方法などについては、最寄りの都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。
建設業の補助金活用事例集
以上、数ある補助金/助成金のなかから、建設業の事業者さまに特におすすめのものを7つ、厳選してご紹介しました。
政府が主導する働き方改革を進めることは、労働者のことを思えば当然、必要です。ただ、現実的な問題として、経営面での深刻なコスト増は避けられないでしょう。
資材や燃料価格の高騰も終わりがみえない昨今、頭を抱える事業者さまも多くおられる筈です。
| 補助金 | IT導入補助金 |
|---|---|
| 建設市場整備推進事業費補助金 | |
| 事業再構築補助金 | |
| ものづくり補助金 | |
| 助成金 | 働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース) |
| 人材確保等支援助成金 | |
| トライアル雇用助成金 |
建設業は日本経済の屋台骨を支える基幹産業であり、インフラや人びとの生活、安全を守るためにも、灯を絶やすことはできません。そのためには、若年世代を育て、産業とともに成長させる必要があることは議論の余地がないでしょう。数ある産業のなかで、政府が建設業の支援に特に注力しているのは、そのためです。
すでに多くの建設業事業者さまが、補助金や助成金を賢く活用して、苦境を乗り越え、大きなビジネスチャンスに変えています。今回、建設業における補助金活用事例をご用意しました。バナーより無料でダウンロードいただけますので、本稿と併せて、ぜひご活用ください!
よくある質問
- Q補助金について返還が求められるケースがあると聞きました。そうした例として、どんなものがありますか?
- A虚偽の申請、補助金の目的外利用や受給額の不当な釣り上げ、関係者へ報酬を配賦するといった不正行為が判明した場合、交付規程に基づき交付決定取消/補助金交付済みの場合は加算金を課したうえで返還を求められます。
- Q事業実施期間内や事業終了後、補助金の補助対象でなくなった場合、補助金を返還することになりますか?
- A事業実施期間内に大企業になった等の事情で補助対象者の要件を満たさなくなった場合には、補助金が支払われません。ただ、事業終了後に大企業になった等で要件を満たさなくなった場合であれば、返還の必要はありません。
- Q2025年6月から改正労働安全衛生法により熱中症リスク管理が事業者に義務づけられます。活用できる補助金はありますか?
- Aエイジフレンドリー補助金は「優先順位の高い労働災害防止対策に要する経費」が補助対象となっており、空調服(ファン付き作業服)やスポットクーラーなどが含まれますので、活用が可能です。
- Q建設業でトラック購入に活用できる補助金はありますか?
- A事業用車両(緑ナンバー)であれば、環境省主管の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」が活用できます。
- Q記事の一覧のほかにも、建設業事業者が利用できる補助金・助成金はありますか?
- A記事内でご紹介した人材確保等支援助成金には、建設キャリアアップシステム等活用促進コースもあります。こちらは、建設キャリアアップシステム(CCUS)等を活用した雇用管理改善に取組む中小建設事業主、CCUSや建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力などの見える化評価制度の普及促進を実施した建設事業主団体に助成するものです。
また、新たに創業・開業・起業する場合には地域雇用開発助成金なども活用できます。助成金を受ける際の要件などの詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
さらに、2025年4月には新たに新事業進出補助金の公募が始まっており、既存事業と異なる事業への挑戦が支援されています。建設業に軸足を置きながら、不動産業やマンション管理、空調設備の管理など、シナジーを生み出す新規事業に乗り出して売上拡大することも視野に入れたいところ。新事業進出補助金は中小企業庁の管轄です。
本記事の関連記事はこちら
・中小企業庁「IT導入補助金」
・中小企業庁「事業再構築補助金」
・中小企業庁「ものづくり補助金総合サイト」
・厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」
・厚生労働省「人材確保等支援助成金のご案内」
・厚生労働省「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
・国土交通省「令和2年 建設業活動実態調査の結果」
・国土交通省「建設産業における女性の定着促進に向けた取組について」
・国土交通省「建設市場整備推進事業費補助金 ~「地域の守り手」となる建設業のICT活用促進~」