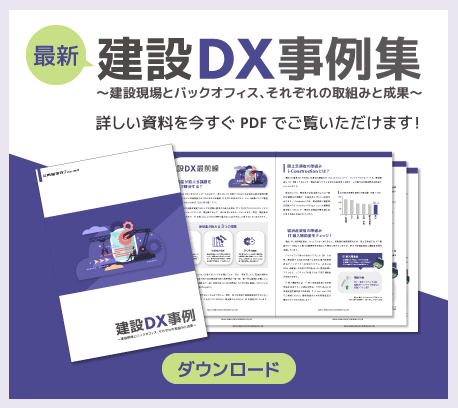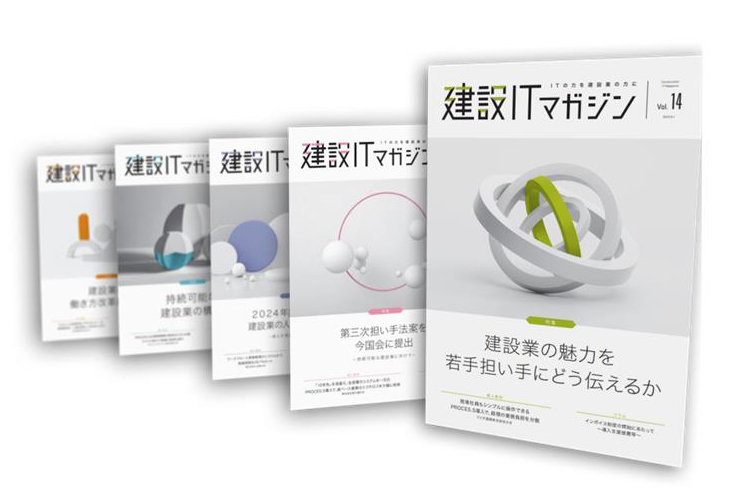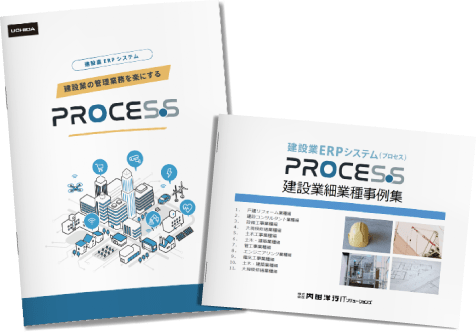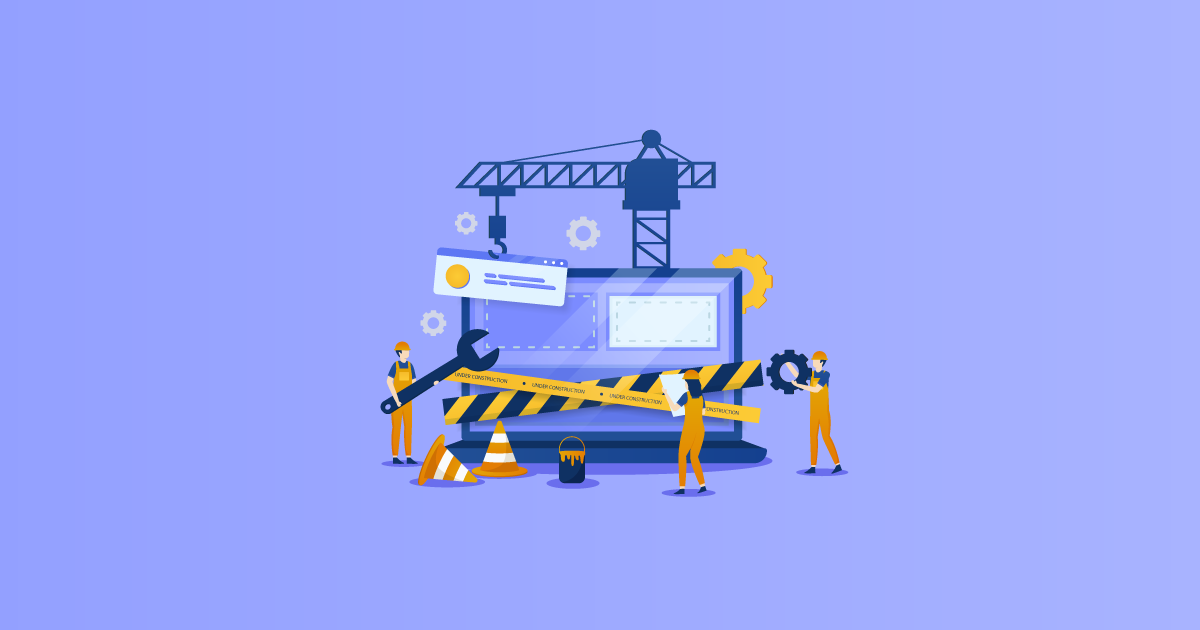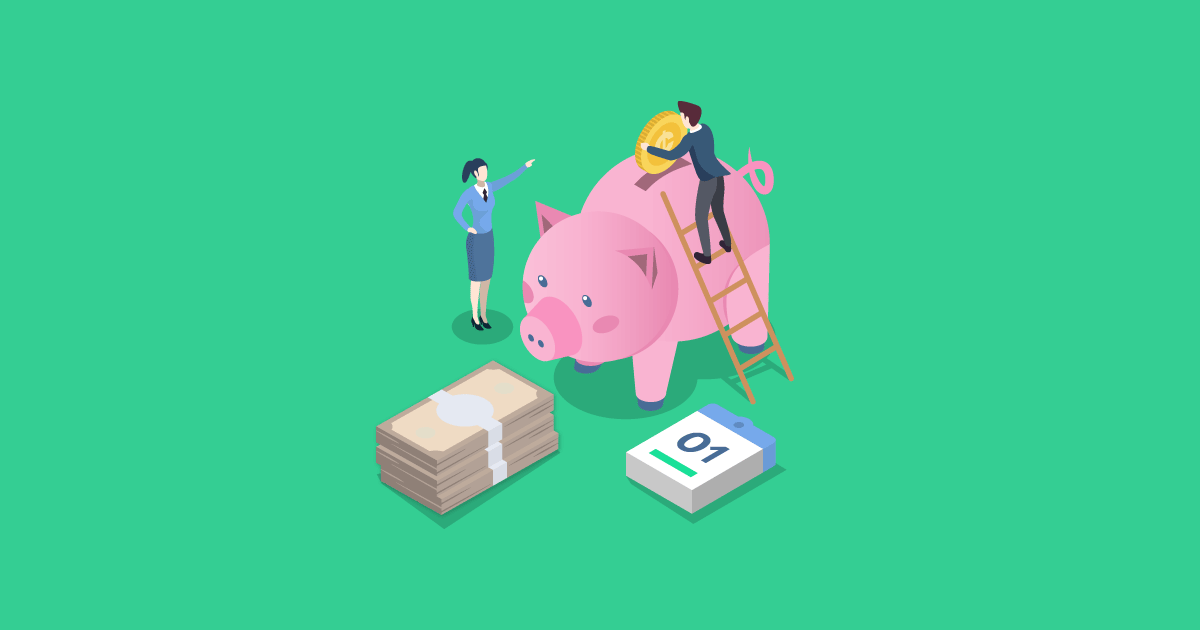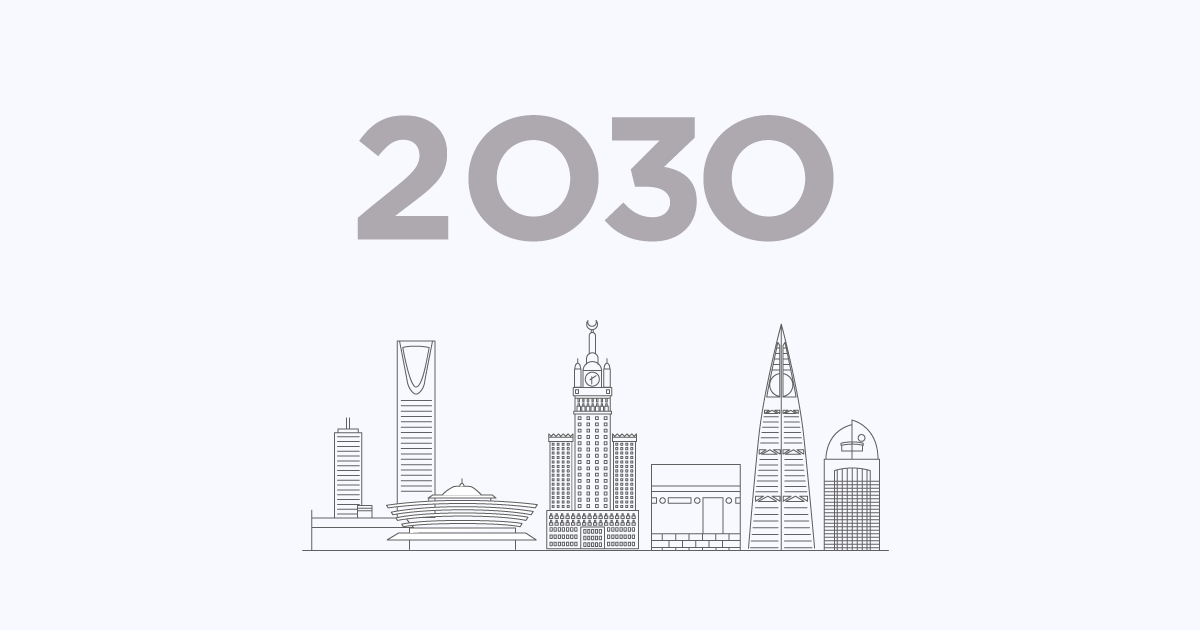2025年の建設業界を統計データをもとに考察
以前、「建設業の最新動向2023」と題しまして、建設業界で増加する人手不足倒産についてお伝えしました。2025年現在、建設業界の倒産件数は引き続き増加傾向にあります。人手不足問題のほか、各種法改正や技術変革を受けて、これまで以上に激動となる2025年の建設業界。本稿では、その最新ニュース・トレンドと成長予測見通しについて、わかりやすくお伝えします!
CONTENTS
01.建設業界の2024年を振り返る
02.建設業界の2025年最新動向
03.建設DXに向けた取組み
04.関連サービスのご案内

建設業界の2024年を振り返る
建設業界にとって、2024年(令和6年)は労働時間の罰則付き上限規制が適用されたことによる建設業の2024年問題のほか、建設業法等の大幅改正、いわゆる第三次・担い手3法の成立と施行、約束手形の支払サイトを60日以内とする下請法の新運用基準発表などを受け、大変革の一年となりました。まずはそれらの主要トピック・最近のニュースを中心に、建設業界にとって2024年がどんな一年だったかをおさらいしてみましょう。
1.建設業の2024年問題
2024年問題とは、改正労働基準法をはじめとする働き方改革関連法の施行により生じる建設業界における諸問題の総称です。2024年4月以降、建設業でも適用された改正労働基準法では、36(サブロク)協定締結後の労働時間上限規制に罰則が追加されたほか、特別条項付き36協定を結んだ場合でも定められた上限を超えた労働を課すことができなくなりました。
建設業では、施工主の意向に応えるため、工期不足に陥るケースが少なくありません。また、天候の影響で工期が延びることもしばしばあり、技能労働者の時間外労働によって補填されてきた経緯があります。改正労働基準法施行後、工期遅れへの対応に苦慮される建設業事業者は、けっして少なくない筈です。
時間外労働を減らすために建設工事現場の増員を図らねばならない場面も多くなるでしょう。現場に入る延べ人数が増加すれば、当然にして労務費のほかにも労務管理や人材確保のコストが重くのしかかります。多くの建設業事業者にとって、深刻な問題といえるでしょう。
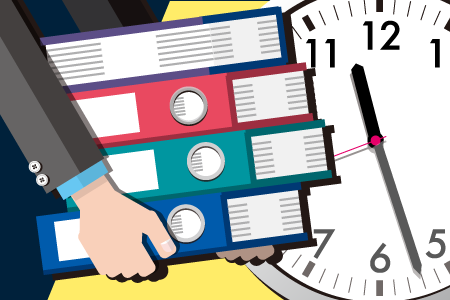
建設業の働き方改革を考える
~2024年問題をどう乗り越えるか?~
2.第三次・担い手3法
建設業の2024年問題を受けて、2024年6月14日に交付されたのが建設業法・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)・品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の一体的改正、いわゆる第三次・担い手3法です。
持続可能な建設業をめざす本改正のなかには、建設業に携わる労働者の処遇改善、資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止、デジタル技術を活用した建設業界の働き方改革を実現するためのさまざまな施策が盛り込まれています。2024年から2025年にかけて三段階で施行されることになっており、建設業界への影響は甚大です。こちらもやはり、注目度が高いトピックのひとつといえるでしょう。

第三次・担い手3法(建設業法等改正2024-2025年)3つのポイント、
事業者の対応は
3.約束手形の支払いサイトが60日以内に
2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイト(決済期間)が60日を超える約束手形や電子記録債権(でんさい)の交付、一括決済方式による支払が行政指導の対象となりました。
手形とは特定の期日に決められた金額を支払うことを約束する有価証券の一種であり、建設業でも馴染み深い商慣習です。一方で、決済期間が長期にわたる手形が下請事業者の資金繰りの負担となっている問題があったため、今回の是正措置がとられました。
また、サイトが60日を超える約束手形は、建設業法第24条の6第3項の「割引困難な手形」に違反するおそれがあるため、建設業では特に注意が必要となります。
今回の基準改正の後にも、紙の手形・小切手を全廃することが予定されており、建設業でもペーパーレス化の対応は必須となるでしょう。
建設業法第24条の6第3項
特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
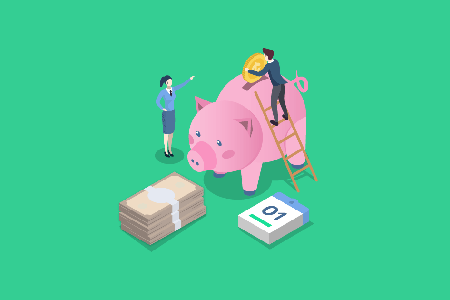
約束手形のサイトは60日以内へ短縮!
期日超は行政指導の対象に
4.建設業で増加する倒産件数
以前の記事でもお伝えしたとおり、建設業界の倒産状況は深刻です。東京商工リサーチの報告では、2024年の企業倒産件数は1万6件で前年比15.1%。そのうち建設業の倒産は飲食業についで多く、1,924件(前年比13.6%増)に達しています。
この数値は、2015年以降の10年間で最多となっています(図1)。前述の2024年問題によるコスト増・人手不足の影響は看過できません。
帝国データバンクのレポートでも、2024年上半期(1-6月)に発生した182件の人手不足倒産のうち、建設業が55件を占めていることが報告されています。人手不足に起因する倒産は、事業規模とも相関があり、従業員数10名未満の小規模事業者で8割以上を占めることも明らかとなっています。

建設業の最新動向2023
~倒産数増加をどう食い止めるか~
建設業界の2025年最新動向
2024年の主要トピックのおさらいを踏まえ、ここからは2025年(令和7年)の建設業界の最新動向について予測してみましょう。まず、市場動向の分析からです。
1.2025年建設業界の市場概況
矢野経済研究所は、国内建設8大市場(住宅・店舗・オフィスビル・ホテル・工場・物流倉庫・学校・病院)について、2025年1月に以下のように報告しています。
2023年度における建設8大市場の市場規模は、工事費予定額ベースで24兆2,989億円(前年度比 104.8%)。新型コロナウイルス禍で延期されていた工事の再開や建設需要の回復もあり、建設市場は拡大傾向で推移しています。
一方で、2021年頃から建設資材価格や労務費の上昇など、建設コストは急激な高騰に見舞われています。調査報告では、労務費高騰の要因として建設業界の人手不足を挙げています。建設業界全体で高齢化や労働者不足が進行することで人員の供給不足が進み、需要の高まりを受けて労務費が上昇しているという建付けです。
2024年度の建設8大市場の市場規模は、物価上昇に伴う建設コスト高騰の影響を受けて拡大の見込み。都心におけるオフィスや商業施設などの大規模再開発や半導体工場などの建設需要は堅調とみられています。
一方で、人口減少による需要縮小や建設費高騰による規模の縮小などマイナス影響も継続するため、市場全体では縮小する見通しとされています。

工事進行基準での収益計算
~資材高騰による見積原価変更の会計処理〜
資材高騰を受けて工期なかばに総原価見積と請負金額が変更された場合の計算例
2.2025年問題
2025年問題とは、団塊世代(第一次ベビーブームである1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となることで起こる、社会保険費の負担増や労働者不足などの一連の問題をいいます(※さらに、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者になると予測されている2030年問題が続きます)。
厚生労働省の推計では、2025年における75歳以上人口は全人口比で18%にのぼるとされており、建設業への影響も無視できません。
国土交通省の報告では、建設業就業者は55歳以上が約36.6%、29歳以下が約11.6%と高齢化が進行しています(図2)。
2023年(令和5年)の実数ベースでは、2022年(令和4年)と比較して建設業就業者数のうち55歳以上が5万人増加する一方で29歳以下は増減なしとなっており、若手世代が入職を控えていることがわかります。
建設業界でも、団塊世代のベテラン層が大量退職することで、間違いなく人手不足が深刻化するでしょう。そうしたなか、売り手市場である若手世代が、労働条件のいい他業種に流出することは避けがたいといえます。
リクルートによる2024年の調査報告でも、2016年比で施工管理の求人が5.04倍、転職者数が3.84倍に増えていることが報告されています。好条件を求めて人材流動が活発化していることが読み解けます。労働環境の整備や採用活動の抜本的な見直しは、建設業にとって喫緊の課題といえるでしょう。

建設業界の2025年問題とは?
人材不足による影響と対策をチェック
3.第三次・担い手3法はどうなる?
2024年に公布された第三次・担い手3法については、すでに段階的に施行されており、2024年9月1日には労働者の処遇確保努力義務化と労務費基準の作成と勧告が、同年12月13日には資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止のほか、ICT活用による現場管理の効率化・現場技術者専任義務の合理化についての規定が施行されています。
残る規定である受注者による原価割れ契約の禁止・工期ダンピング対策の強化などについても2025年12月の施行が予定されています(図3)。原価割れ契約や工期ダンピングについては、発注者側だけでなく受注者側も禁止されるため、業界への大きな影響が予測されます。
第三次・担い手3法を受け、国土交通省は建設Gメンの体制強化・活動強化を掲げています。建設工事の取引実態を調査する建設Gメンについて、令和5年度72名に対し令和6年度には135名と大幅に増員されました。違反疑義情報は3万業者に及ぶ毎年調査と各地方整備局などに設置された通報窓口「駆け込みホットライン」によって把握されます。建設Gメンは、これらの情報をもとに、実地調査と改善指導を行なうことが任務となります。

第三次・担い手3法(建設業法等改正2024-2025年)3つのポイント、
事業者の対応は
4.建設コスト(労務費・材料費)の動きは?
すでにお伝えしたように、2021年以降、世界的な原材料・エネルギー価格高騰や円安の影響を受けて、建設工事の資材価格は高騰しています。一般社団法人 日本建設業連合会によれば、2025年1月の土木部門資材価格は2021年1月と比較して36%上昇しているとのこと。資材価格の高騰傾向は、いまだ沈静化の様相をみせません。
また、政府の賃上げ方針や第三次・担い手3法の施行を受けて、建設工事現場で働く建設技能労働者の賃金も上昇しています。国土交通省は、2025年3月から適用する公共工事設計労務単価について、全国全職種単純平均で前年度比6.0%引上げることを発表しています。2025年は材料費のみならず、労務費も引き続き上昇傾向が続くことがわかります。
なお、日本建設業連合会は、材料費と労務費の上昇により、土木分野の建設コストは直近48カ月で25~28%上昇していると試算しています。

建設業の労務費とは?
人件費との違いや計算方法まで徹底解説!
建設DXに向けた取組み
2025年は深刻な人手不足とともに、材料費・労務費についても高騰が維持される見通しです。もちろん、それらの課題を乗り越えるべく、政府主導でさまざまな施策が進められています。
1.i-Construction 2.0
2024年4月、国土交通省は「建設現場のオートメーション化」に向けた取組みとして、i-Construction 2.0を策定しました。
これはいうまでもなく、ICT活用を建設現場に導入することによって建設生産システム全体の生産性向上を図る取組みとして2016年から推進されてきたi-Constructionの発展形です。
i-Constructionとは?
将来的な建設業の担い手不足に備え、国交省が2016年度から推進してきたICT活用の取組み全般を指す。i-Constructionでは、建設現場の生産性向上を目指し、あらゆる建設生産プロセスでICTを活用することで、建設現場の生産性を2割向上することを目標として掲げてきた。2024年、国土交通省は、直轄事業においてICT施工による作業時間の短縮効果をメルクマールとした生産性向上比率(対2015年度比)が21%となったこと報告している。
i-Constructionは数値目標を達成し、大きな成果を収めました。三次元データや ICT 建設機械の活用など、デジタル技術の活用も普及が進みました。2023 年度からは直轄土木工事において、建設工事で扱う情報をデジタル化する BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)活用を原則化するなど、建設業の在り方を変革していく体制は整いつつあります。
一方で、人口減少下において将来にわたり持続的にインフラ整備・維持管理を実施するためには、これまでのICTの活用から自動化にシフトしていくことが必要不可欠です。
「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」を3本の柱とするi-Construction 2.0では、2040年度までに少なくとも省人化3割、すなわち1.5倍の生産性向上を目指すことが目標に掲げられています。

【最新】建設DX事例
~「2025年の崖」対策は万全ですか?~~
2.第三次・担い手3法を受けた変化
第三次・担い手3法においても、ICT活用による生産性向上の施策が盛り込まれており、2024年12月13日から施行されています。それを受けて、2025年以降は大きな業務効率化が見込まれます。具体的には、現場技術者の専任義務の合理化とICTを活用した現場管理の効率化がそれにあたります。
現場技術者の専任義務の合理化
建設業法第26条では、施工水準を担保するために技術力を有する技術者(監理技術者・主任技術者)を工事現場ごとに配置することが求められています。従来、こうした技術者には、特定の工事に対して専任であることが求められてきました。2024年12月13日以降、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認ができる場合に、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については、2現場まで兼務できるようになっています。
ICTを活用した現場管理の効率化
第三次・担い手3法のなかで、工事施工に関する情報システム整備などの ICT 活用に関する努力義務が新たに規定されるとともに、特定建設業者が ICTの活用に関し下請業者を指導する努力義務が新たに規定されています(建設業法第25条の28)。
その他、今回の一連の法改正を受けて、国によって「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針(ICT指針)」が作成・公表されました。i-Construction 2.0の推進も含めた建設業全体のICT化実現をめざすというもので、建設工事現場だけでなく、バックオフィスのICT化についても大きく頁が割かれています。
例えば電子入札・電子契約について、本指針では建設業の業務効率化に資するものと位置づけられており、下請事業者における導入を促進するとともに公共発注者についても導入が遅れている市区町村を中心に取組みを強化すべきである旨が記載されています。

PickUp!
建設業こそ電子契約を導入すべき3つの理由
【2024最新】
電子契約の適法性、導入メリットから選定のポイントまで
関連サービスのご案内
建設業は地域の守り手ともいわれ、インフラの維持や整備において、きわめて重要な役割を担う産業です。人口減少下においても将来にわたり事業を維持していくために、少ない人数でも仕事を遂行できるよう、業務の在り方そのものを変革していく必要があります。政府のICT指針にもあるように、それはけっして、建設工事現場だけの話ではありません。
工事現場のDXと両面で、バックオフィス業務もまた、ICTを駆使した業務変革が求められています。こうした課題へのソリューションとして、建設業ERPシステム“PROCES.S”がおすすめです。
PROCES.Sは、建設業の基幹業務を一元化し、業務効率向上を図るとともに、建設業の特殊な会計基準にも対応。材料費や労務費が高騰するなかでも、精緻な原価管理で適正利益確保をご支援するほか、記事にもあった電子契約システム、さらに勤怠管理システムなど、さまざまなシステムと連携することでバックオフィス業務の全体最適を実現します。2025年、さまざまな課題に見舞われる建設業事業者さまにとって、最適のソリューションといえるシステムです。
製品資料のほか、建設業の最新情報をお伝えする“建設ITマガジン”がございます。いずれもPDFダウンロードにてすぐにご覧いただけますので、ぜひ貴社の課題解決にお役立てください!
本記事の関連記事はこちら
・経済産業省「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します」
・東京商工リサーチ「建設業の倒産 過去10年間で最多 資材高、人手不足に「2024年問題」が追い打ち」
・帝国データバンク「人手不足倒産、過去最多ペース「2024 年問題」が直撃」
・リクルート「建設業界に迫る「2024年問題」「施工管理」求人、2016年比で5.04倍に増加」
・矢野総合研究所「国内建設8大市場に関する調査を実施(2025年)」
・国土交通省「改正建設業法について~改正建設業法による価格転嫁・ICT活用・技術者専任合理化を中心に~」
・国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について~今回の引き上げにより、13年連続の上昇~」
・一般社団法人 日本建設業連合会「建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い(2025年2月版)」
・国土交通省 「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化~ 」
・国土交通省 「i-Construction 2.0 ~建設現場のオートメーション化に向けて~」
・国土交通省「情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針」