株式会社新和
- 事業内容
- 建築、内装、病院検査室防護・シールド工事
- 設立
- 1977年
- 資本金
- 1,000万円
- 社員数
- 30名(2025年3月現在)
- 所在地
- 東京都大田区仲池上 2-11-5
- Webサイト
- https://shinwa1.jp/
- 導入システム
- 建設業ERPシステムPROCES.S
まもなく創業から半世紀を迎える株式会社新和は、管工事業のほか、内装工事、X線防護工事など、多様な事業を展開してきた。とりわけMRI室の電磁波シールド工事は、1980年代のMRI黎明期から携わり、特殊施工の技術とノウハウを蓄積。「信頼関係は一夜にしてならず」の理念のもと、設備のプロフェッショナルとして、たしかな施工で顧客の信頼を築いてきた。

△ 左:MRI室冷水装置配管改修工事、右:レントゲン室工事

△ 左:アンギオ室天井補修工事、右:電波シールド工事床銅板はり
現在は首都圏を中心に、医療機関の設備・建築内装を含めた放射線エリアの工事を受注し、業績を拡大。東京大学医学部附属病院や帝京大学医学部附属病院、新築工事から携わった国際医療福祉大学成田病院など、大規模病院の施工実績も数多い。サービス品質向上や業務改善にも積極的に取り組み、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」認証を2004年から継続して取得している。

△ 静岡がんセンター_ルミナススカイシーリング取付工事
株式会社新和は、財務・売上・原価の管理をそれぞれ別々のツールで行っていました。これらは相互に連携されておらず、重複入力によるミスや、ツールごとのデータに差異が生じるという課題に直面していました。これらを解決するために、システム導入によるデータ一元化を検討し、最終的に内田洋行ITソリューションズ(以下、ITS)の建設・工事業ERPシステム「PROCES.S」を選びました。ITSのサポートを受けながらカスタマイズを行い、導入後は入力業務の工数が半減したほか、業務の可視化や原価意識醸成などの効果が生まれています。
システム導入の課題と効果
導入前の課題
- 財務・売上・原価の管理が別々のツールで行われ、相互に連携されていなかった
- 重複入力が発生しており、入力ミスも少なくなかった
- 3つのツールのうち「どのデータが正しいかわからない」という状況が生じていた
導入後の効果
- 入力作業の工数が半減 請求書発行などの手作業も減り効率化が進展
- 管理部の業務が可視化され、部員が事業全体を意識して業務に取り組めるように
- 現場社員が直接帳票を閲覧できるようになり、原価意識が醸成された
導入の背景
財務・売上・原価を別々のツールで管理
重複入力によるミスが生じていた
「PROCES.S」を導入しようと思った背景を教えてください。
当社は財務・売上・原価を別のツールで管理しており、それらが連携されていない点に課題を感じていました。財務は会計ソフト、売上と原価はそれぞれ異なるExcelシートで、別々に入力を行う仕組みです。ある時、会計ソフトと売上シートの金額に差異があることが発覚。調べてみると、売上シートの方にだけ、金額訂正が入っていたことがわかりました。原価シートに関しても、請求書に記載されているお取引先名を見誤って、似た名前の別のお取引先の欄に数字を入力するミスも散見されました。
このように、会計ソフトと売上シート、原価シートのそれぞれに都度入力を行わなければならないことが、ミスの原因になっていました。また、それらがいつでも書き換えられてしまうことで、「どのデータが正しいかわからない」という状況。この点に危機感を抱き、情報の一元管理ができるシステムの導入を経営層に提案し、検討をはじめたのです。
導入のポイント
建設業に特化し、サポート体制や法改正対応も充実しているPROCES.Sを選んだ
PROCES.Sを選んだ決め手は何でしたか。
管理部員にさまざまなシステムを調べてもらいましたが、どれも決め手に欠けていました。そんな中で候補に浮上したのが、中途入社の社員が前職で使っていた「PROCES.S」。建設業に特化したシステムであること、ITS担当者の対応が早く、サポート体制が充実していること、そして法改正などにもスピーディーに対応してアップデートされるという点に魅力を感じました。
また、誰も知らないシステムを導入するよりも、前職で日常的に活用していた社員がいる「PROCES.S」のほうが安心感がありました。他にも価格面でアドバンテージがあるシステムはあったものの、最終的には信頼のおける「PROCES.S」を選びました。
「PROCES.S」の導入を決めてから運用を開始するまでの流れを教えてください。
導入を決めた2021年の秋から、まずはデモという形で「PROCES.S」の機能を確認する作業をスタート。「PROCES.S」にはたくさんのモジュールがありますが、一度にすべてを導入するのはコスト的にも厳しいため、段階的に導入を進めていくことにしました。
ITSに相談して実現したことを教えてください。
「PROCES.S」を立ち上げたトップ画面で、先方の注文番号、当社の見積もり番号、担当者や得意先コードなどの項目が、工事ごとに一覧で表示される状態にしたいと要望しました。集計や帳票出力を考えて、できるだけ細かい項目まで網羅しておきたかったのです。
その際、ITSの担当者から、項目が細かすぎると実際の運用でデメリットが生じるので、少し絞ったほうが良いという提案がありました。「他社さんはこんなふうに運用されていますよ」「ここはなくても困らないかもしれません」と、実務の観点で的確な意見をいただけたのは助かりました。おかげで、当社にとって必要十分なカスタマイズができたと思っています。
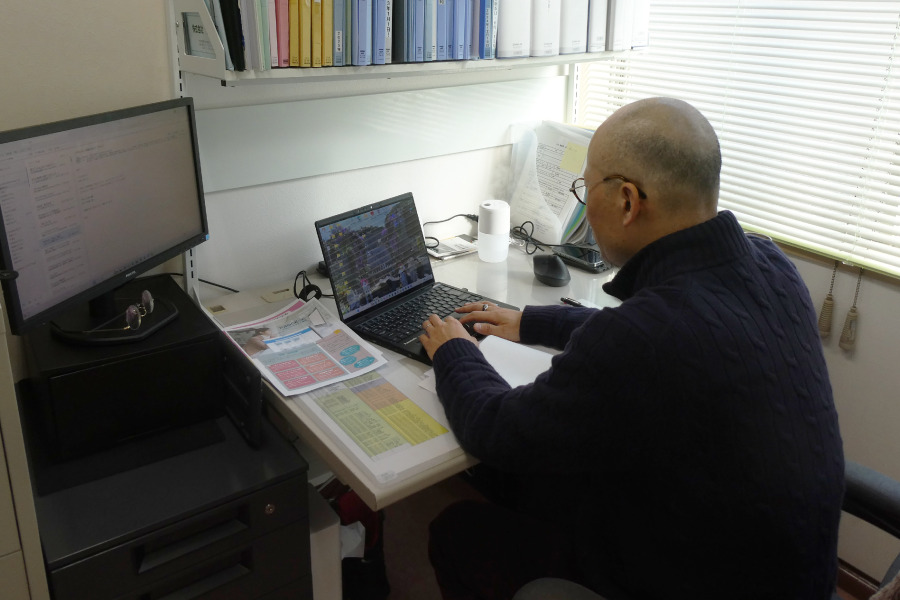
△ 株式会社新和オフィスでのご様子
導入の効果と今後の展開
データ一元化で入力工数が半減
管理業務が可視化され、現場への原価意識浸透の効果も
実際にPROCES.Sの運用を始められて感じたことや、得られた成果について教えてください。
今までは3つのツールに入力していたものが一元化されたので、入力の工数は半分以下になりました。また、請求書の発行についてもExcelから「PROCES.S」に移行。今までのようにファイルをコピーして、金額を入れて…という手作業をしなくて良くなったので、効率化が進みました。
「PROCES.S」への一元化で、工期の修正などがあれば各帳票にきちんと反映されるようになりましたし、経理側で「請求書が発行されているか」「入金処理が終わっているか」なども漏れなく把握できるようになりました。また、工事経歴書などの書類を簡単に出力できますし、CSV化したものを加工して資料作成できるのは助かります。
新しいシステムなので、当初は部内に抵抗感もありましたが、ITSとの打ち合わせを重ねる中で「こんなこともできるようになるんだ」と少しずつ不安が解消されていきました。「変えなくてもなんとかなるよね」では、いずれ限界が来ます。ITSの力を借りて、このタイミングで導入できたのは本当に良かったです。
そのほかにも、PROCES.S導入による良い影響はありましたか?
部員が、それぞれの担当だけでなく、事業全体を理解できるようになったことですね。分業が進んでいる部署なので、これまでは「請求担当は請求書のことだけを見ている」状態でした。「PROCES.S」によってその垣根が取り払われたので、請求書を発行したあとの経理的処理のこと、原価や労務費がどうなっていて、そこから利益がどのくらい上がるのかなど、管理部の業務の全体像が可視化されたのは大きな収穫です。
現場側にも変化が生まれています。工事部の社員も「PROCES.S」で帳票を閲覧できるので、原価表で現状の原価を確認しながら業務を進める動きが見られるようになってきました。
ITSの担当者には、どのような印象をお持ちですか?
営業の方は、前職で「PROCES.S」を使っていた社員とも長い付き合いですし、「彼がいれば安心」という信頼感がありますね。SEの方は、導入後もつまづいた部分があれば丁寧に教えてくれるので、疑問をすぐに解消できます。
さまざまな企業の課題解決をしているITSはたくさんの「引き出し」を持っているので、「こうしたらいいですよ」と、私たちの事情に合った提案を積極的にしてくれます。臨機応変な対応をしてくれる担当者に巡り合えたことに感謝です。
今後、PROCES.Sをどのように活用していきたいですか?
「PROCES.S」にはさまざまな機能があって、ありとあらゆる帳票を出力できるので、フル活用していきたいですね。今考えているのは、働き方改革への活用。PROCES.Sで原価と売上を紐づけることができたので、工事部の各チームが売上・利益にどのくらい貢献してくれたかを見える化することで、「自分たちはこの部分をもっと改善しよう」と社員が自ら考えられるような仕組みを整えていきたいと思っています。













